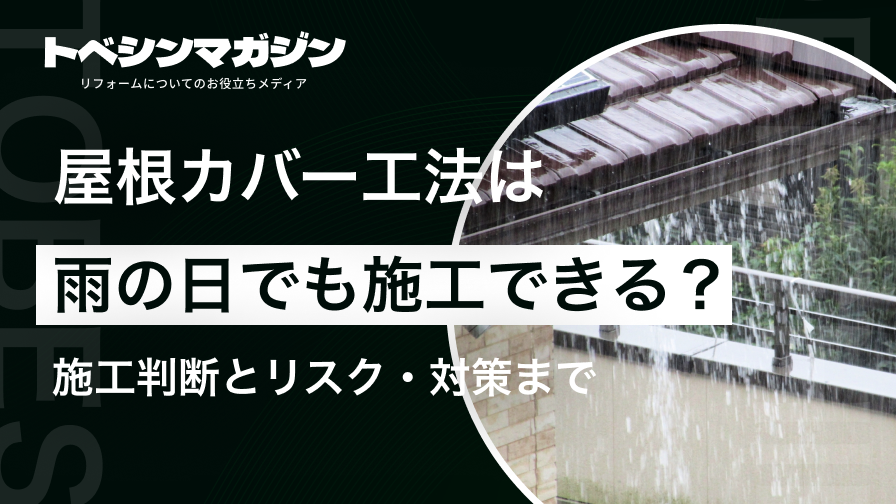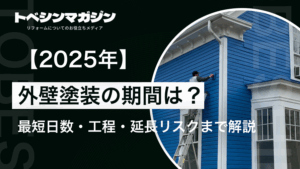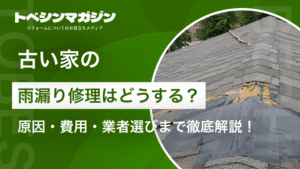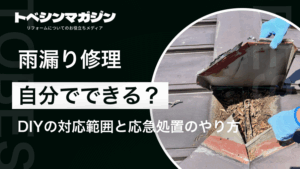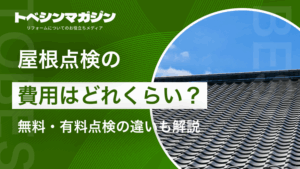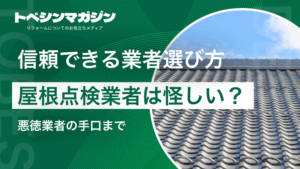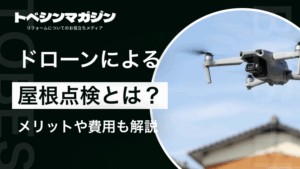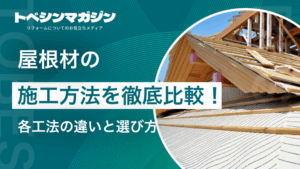「雨の日でも屋根工事はできるのかな?」
「カバー工法の途中で雨が降ったらどうなるんだろう」
「雨の予報が出ているけど、工事を延期すべき?」
屋根リフォームを検討中の方にとって、天候は大きな懸念事項です。特に雨の多い時期や急な工事が必要な場合、工期の遅れが不安になるものです。
屋根カバー工法は既存の屋根を残したまま新しい屋根材を重ねる工法ですが、基本的に雨天時の施工には様々なリスクが伴います。工事中の安全性や施工品質を確保するためには、天候への適切な対応が不可欠です。
どの工程なら雨天でも施工可能か、どの段階で中止すべきかを理解しておくことは、トラブルのない屋根リフォームを実現するために重要な知識となるでしょう。
この記事では、屋根カバー工法における雨天時の施工判断基準からリスク要因、効果的な対策方法まで詳しく解説します。
雨の日の屋根工事に関する疑問を解消し、安心して屋根リフォームを進めるための参考にしてください。
この記事のポイント
- 既存屋根材を全撤去し新材料に交換する大規模工事
- 屋根カバー工法は施工内容によって雨の日でも可能な場合もある
- スムーズに工事を進めたいなら晴れの日がベスト

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。
専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
屋根カバー工法は雨の日でも施工できる?
屋根カバー工法は、既存の屋根材を撤去せずに新しい屋根材を重ねる工法です。
「雨の日でも施工できるのか」という疑問について結論から言うと、天候に左右されにくい工程もありますが、基本的には晴れた日に施工するのがベストです。
屋根カバー工法の施工工程と雨の程度による施工判断について詳しく見ていきましょう。
屋根工事は雨の影響を強く受けるため、施工業者は天候を常に注視しながら作業を進めます。特に防水性能に関わる工程では、天候の影響が施工品質を大きく左右することがあるでしょう。
屋根カバー工法の基本的な施工工程
屋根カバー工法の一般的な施工工程は、足場の設置から始まり、既存屋根の点検・補修、防水シートの施工、新しい屋根材の設置、最後に仕上げ・点検という流れで進みます。
足場設置は安全対策として必須の工程で、通常2日程度かかります。その後、既存屋根の状態を確認し、必要に応じて補修を行います。
次に重要となるのが防水シート(ルーフィング)の施工です。これは屋根防水の主役とも言える工程で、雨水の侵入を防ぐ重要な役割を担っています。
続いて新しい屋根材(ガルバリウム鋼板など)を設置し、最後に仕上げと点検を行って工事は完了します。全体の工期は一般的に5~7日程度ですが、天候によって変動することがあります。
雨の程度による施工判断
雨の程度によって、屋根カバー工法の施工可否は大きく変わります。小雨程度であれば一部の作業は可能ですが、本格的な雨の場合はほとんどの工程が困難になるでしょう。
軽い雨の場合、足場設置や屋内での資材準備など一部の作業は継続できます。また、ルーフィング施工後であれば、多少の雨でも作業を進められることもあります。
しかし、中程度から強い雨の場合は、作業員の安全確保や施工品質維持のため、ほとんどの工程で作業中止の判断がなされます。
特に金属屋根(ガルバリウム鋼板など)の場合、雨で濡れると非常に滑りやすくなり危険です。
常識的な屋根リフォーム業者であれば、翌日の天気予報を確認し、雨が予想される場合は事前に養生や工程調整を行います。急な天候の変化にも対応できるよう、柔軟な工事計画を立てることが重要です。
屋根カバー工法で雨の日に施工可能な工程
屋根カバー工法においても、雨の日に施工できる工程とできない工程があります。工事を効率的に進めるためには、天候に合わせた作業計画が重要です。
ここでは、雨天時でも比較的施工可能な作業について解説します。
雨天時でも工事を進められる工程を把握しておくことで、工期の遅延を最小限に抑えることができるでしょう。
足場設置や資材準備などの準備作業
小雨程度であれば、足場の設置作業は比較的問題なく進められます。足場設置は屋根本体の工事とは異なり、多少の雨でも作業が可能な場合が多いです。
また、資材の荷揚げや荷下ろしなどの準備作業も、軽度の雨であれば実施できます。
ただし、強風を伴う雨の場合は安全面から作業を中止することが一般的です。足場が滑りやすくなるため、作業員の転落リスクを避けるための判断が必要になります。
足場設置は一般的に屋根工事全体の工程で2日程度を要する作業ですが、天候に合わせて柔軟に日程調整することで、全体の工期への影響を最小限に抑えることが可能です。
ルーフィング施工後の一部作業
防水シート(ルーフィング)の施工が完了した後であれば、多少の雨が降っても一部の作業は継続できます。ルーフィングは防水性が高いため、この段階で雨が降っても下地や躯体への影響は比較的少ないでしょう。
屋根材のカットや準備作業など、屋根の上での作業以外の部分は、軽い雨であれば実施可能です。また、軒先や破風板などの付帯部の作業も、ルーフィング施工後であれば雨天時でも進められる場合があります。
ただし、ルーフィングの上を歩くと滑りやすくなるため、作業員の安全を確保するための十分な注意が必要です。常に天気予報をチェックしながら、作業の継続か中止かを判断することが重要になります。
屋内での事前準備作業
雨天時でも屋内で行える準備作業は数多くあります。屋根材のカットや事前組み立てなど、屋内で可能な範囲の作業を進めることで、晴れた日の効率的な施工に備えられます。
また、工事に必要な資材の搬入や配置なども、雨の日に行うことができる準備作業です。さらに、施工計画の見直しや詳細な打ち合わせなど、実際の施工以外の作業も雨天時に行えます。
このように屋内での準備作業を雨の日に集中して行うことで、晴れた日に本格的な屋根作業を効率よく進めることが可能になります。天候に左右されない作業を適切に組み込んだ工程計画を立てることが、全体の工期短縮につながるでしょう。
屋根カバー工法で雨の日に施工できない工程
屋根カバー工法において、雨天時に施工を避けるべき工程があります。これらの工程を雨の日に強行すると、施工品質の低下や安全面でのリスクが高まるため注意が必要です。
ここでは、雨の日に施工すべきでない重要な工程について解説します。
これらの工程は晴れた日に行うことで、高品質な屋根工事を実現できます。
防水シートの設置作業
防水シート(ルーフィング)の設置は、雨の日には行うべきではない重要な工程です。雨に濡れた状態でルーフィングを施工すると、密着性が低下し、防水性能が十分に発揮できなくなる可能性があります。
防水シート自体は雨に濡れても機能を損なわないように設計されていますが、施工時の接着が不十分になると、長期的な防水効果が低下するリスクがあります。
特に接着剤を使用する部分では、湿気によって接着力が弱まることがあるでしょう。
また、濡れた状態で防水シートの上を歩くと、シートが滑ったり破れたりする可能性もあります。防水シートの施工は屋根工事の要となる工程であるため、必ず晴れた日に丁寧に行うことが重要です。
屋根材の固定作業
新しい屋根材を固定する作業も、雨天時には避けるべき工程です。特に金属屋根(ガルバリウム鋼板など)は雨で濡れると非常に滑りやすくなり、作業員の転落事故のリスクが高まります。
また、雨天時に屋根材を固定すると、屋根材と下地の間に水分が残り、後々のさびや腐食の原因となることがあります。
さらに、濡れた状態では屋根材の適切な位置決めや固定が難しくなり、施工精度が低下する恐れがあります。
屋根材の固定作業は屋根の耐久性や美観に直接関わる重要な工程です。雨天時の施工を避け、晴れた日にしっかりと時間をかけて行うことで、長期間にわたって高い性能を発揮する屋根を実現できるでしょう。
下地の状態確認と補修作業
既存屋根の下地の状態確認や補修作業も、雨天時には適切に行えません。雨で濡れた下地は状態が正確に判断できず、補修が必要な箇所を見落とす可能性があります。
特に木材の腐食や劣化の程度は、乾燥した状態でなければ正確に判断できないことが多いです。下地が濡れた状態で工事を進めると、「劣化」や「腐朽」、「カビ」の原因となることもあります。
下地の補修作業においても、接着剤や補修材の効果が雨で低下する可能性があります。適切な下地処理は屋根の耐久性を左右する重要な要素です。
必ず晴れた日に十分な時間をかけて確認と補修を行い、安心できる土台を作ることが大切です。
雨の日の屋根カバー工法のリスク
雨の日に屋根カバー工法を行うことには、いくつかの重要なリスクが伴います。これらのリスクを事前に理解しておくことで、適切な判断と対策が可能になります。
ここでは、雨天時の屋根カバー工法における主な3つのリスクについて詳しく解説します。
これらのリスクを把握し、適切に対応することで、屋根工事の品質と安全性を確保することができるでしょう。
リスク1:作業員の安全面
雨の日の屋根工事で最も深刻なリスクは、作業員の安全に関わる問題です。
雨で濡れた屋根の表面は非常に滑りやすくなり、転落事故のリスクが大幅に高まります。特に金属屋根(ガルバリウム鋼板など)の場合、雨天時の滑りやすさは顕著です。
さらに、雨天時は視界が悪くなり、足場が不安定になることで、作業員のバランスを崩しやすくなります。
また、雨に濡れた工具や資材を扱うことも危険度を増す要因となります。実際に屋根工事現場では、雨の日の作業による死亡事故も報告されています。
安全帯を使用していても、雨天時は十分な安全確保が難しいため、良識ある業者は雨の日の屋根作業を避けるのが一般的です。
作業員の安全を最優先に考え、無理な作業スケジュールを組まないことが重要です。
リスク2:防水性能への影響
雨天時の施工は、屋根の防水性能に重大な影響を及ぼす可能性があります。
特に防水シート(ルーフィング)の施工において、雨水が下地と防水シートの間に入り込むと、密着不良を起こし防水機能が低下します。
また、濡れた状態で防水シートを施工すると、接着剤の効果が十分に発揮されず、後々の雨漏りの原因になることがあります。
さらに、屋根材と下地の間に水分が残ると、木材の腐食や金属部分のさびを促進させる恐れもあるでしょう。
雨天時に無理に施工を進めると、見た目には問題がなくても、施工後数か月から数年で不具合が発生する可能性があります。防水性能は屋根の最も重要な機能であるため、適切な条件下での施工が不可欠です。
リスク3:工期遅延の可能性
雨天が続くと、必然的に工事の中断や延期が必要になり、当初予定していた工期よりも長引く可能性があります。
特に梅雨時期や台風シーズンなど、雨が多い時期に工事を計画している場合は、工期の遅延リスクを考慮する必要があります。
一般的な屋根カバー工法の工期は5~7日程度ですが、天候不良により1日あたりの作業時間が短くなったり、完全に作業を中止せざるを得なかったりすることで、実際の工期は2倍以上になることもあります。
また、工期が延びることで、追加の足場設置費用や人件費がかかる場合もあるでしょう。
契約時に雨天時の対応や工期延長に関する取り決めを明確にしておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
工事計画時には、天候による遅延を考慮した余裕あるスケジュールを立てることが賢明です。
【雨の日】屋根カバー工法と葺き替えの違い
雨の日の屋根リフォームを考える際、カバー工法と葺き替え工法ではどのような違いがあるのでしょうか。
両工法は雨天時に異なる特性を持ち、工期やコスト、住宅の保護という観点でそれぞれメリット・デメリットがあります。
ここでは、雨天時における両工法の主な違いについて解説します。
適切な工法を選ぶことで、雨天時のリスクを最小限に抑え、満足のいく屋根リフォームを実現することができます。
雨天による工期への影響の差
カバー工法と葺き替え工法では、雨天時の工期への影響が大きく異なります。葺き替え工法は既存の屋根材を全て撤去するため、屋根が一時的に露出する期間があり、この間に雨が降ると工事が大幅に遅延する可能性があります。
一方、カバー工法は既存の屋根をそのまま残すため、工事途中で雨が降っても影響を受けにくいという特徴があります。特にルーフィングの施工後であれば、一部の作業は軽い雨でも継続できることもあるでしょう。
葺き替え工法の場合は天候不良で工期が2倍以上になることもありますが、カバー工法であれば比較的工期の遅延を抑えられる可能性があります。
ただし、どちらの工法でも防水シートの設置など重要な工程は晴れた日に行う必要があります。
雨天時の施工コストへの影響
雨天時の施工は、両工法ともコストに影響を与える可能性がありますが、その影響度合いには違いがあります。
葺き替え工法では雨天による工期延長が顕著なため、足場の設置期間が長くなり、追加費用が発生しやすくなります。
また、葺き替え工法では屋根を撤去した後に雨が降った場合、応急的な雨養生が必要になり、その費用も発生する可能性があります。カバー工法ではこうした大掛かりな養生は比較的少なくて済むでしょう。
ただし、どちらの工法でも雨天による工期延長に伴う追加費用について、契約時に明確に確認しておくことが重要です。
一般的には、天候による工期の遅れで数日程度の延長であれば、追加費用は発生しないケースが多いようです。
雨天時の住宅保護の違い
雨天時の住宅保護という観点では、両工法に明確な違いがあります。
葺き替え工法は既存の屋根材を全て撤去するため、工事中に雨が降ると住宅内部への雨水の侵入リスクが高まります。急な天候の変化に対して速やかに防水シートなどで養生する必要があるでしょう。
対してカバー工法は既存の屋根材がそのまま残るため、工事途中でも基本的な防水機能は維持されます。これは特に突然の雨に対する安全弁となり、住宅内部を保護する上で大きなメリットとなります。
ただし、カバー工法でも施工不良があると雨漏りのリスクはあるため、どちらの工法を選ぶにせよ、信頼できる業者による丁寧な施工が重要です。特に雨が多い時期の工事では、どのように住宅を保護するかを事前に業者と十分に話し合っておくことが大切でしょう。
雨天時の屋根カバー工法の対策方法
雨天時に屋根カバー工法を行う場合、適切な対策を講じることでリスクを最小限に抑えることが可能です。施工品質を確保し、安全に工事を進めるためには、事前の準備と緊急時の対応策が欠かせません。
雨天時の屋根カバー工法における3つの効果的な対策方法について詳しく解説します。
これらの対策を適切に実施することで、雨天時のリスクを大幅に軽減し、高品質な屋根工事を実現することができるでしょう。
対策方法1:防水シートによる養生
雨天時の屋根工事で最も基本的かつ重要な対策は、防水シート(ブルーシートなど)による適切な養生です。工事中に急な雨が降ってきた場合、迅速に屋根全体をブルーシートで覆い、雨水の侵入を防ぐ必要があります。
特に既存屋根の状態確認や一部撤去を行った後は、下地や構造材が露出する可能性があるため、常に養生材を用意しておくことが大切です。
また、養生シートは単に被せるだけでなく、風で飛ばされないように適切に固定することも重要です。
養生作業は工事の進行状況に応じて随時見直し、必要に応じて補強することが必要です。雨養生は緊急時の一時的な対策ですが、これをしっかり行うことで、屋根材や下地の劣化を防ぎ、後の施工品質を確保することができます。
対策方法2:段階的な施工計画の立案
雨のリスクを考慮した段階的な施工計画を立てることも効果的な対策です。屋根全体を一度に施工するのではなく、小さな区画ごとに作業を進めることで、急な雨に対応しやすくなります。
例えば、一日の作業量を防水シートの施工までで区切り、確実にその日のうちに防水層を完成させるような計画を立てると良いでしょう。これにより、作業の途中で雨が降っても、既に施工済みの部分は保護された状態になります。
また、雨が予想される日は屋内での準備作業に充て、晴れた日に屋根上での作業を集中して行うなど、工程の順序を工夫することも大切です。段階的な施工計画は、予期せぬ雨によるダメージを局所的に抑え、工事全体への影響を最小限に抑える効果があります。
対策方法3:工期調整と天気予報の活用
屋根工事を成功させるための重要な対策として、天気予報を活用した工期調整が挙げられます。施工前には必ず数日先までの天気予報をチェックし、降水確率が高い日は作業を避けるよう計画しましょう。
特に防水シートの施工や屋根材の固定など、雨に弱い重要な工程は、晴れが続く日に集中して行うことが理想的です。最近は気象予報の精度も向上しているため、こうした予報を積極的に活用することが可能です。
また、工事の契約段階で、天候不良による工期延長の可能性について依頼主と話し合っておくことも重要です。余裕を持った工期設定をしておくことで、無理な作業を避け、安全で品質の高い施工を実現することができるでしょう。
屋根カバー工法後は雨の音が変化するのか?
屋根カバー工法後は屋根材の種類によって雨音が変化する可能性があります。金属屋根材(ガルバリウム鋼板など)を使用した場合、雨音が大きくなることがある一方、既存屋根と新しい屋根の二重構造により遮音効果が向上して雨音が軽減されることもあります。
雨音が気になる場合は施工前に業者と相談し、遮音材の設置も検討すると良いでしょう。実際の雨音の変化は屋根材の組み合わせや施工方法によって異なるため、事前に施工事例などを確認しておくことをおすすめします。
屋根カバー工法を選ぶ際は防水性や断熱性だけでなく、こうした生活環境の変化も考慮することが大切です。
静かな環境を好む方や音に敏感な方は、業者に雨音対策の実績や方法について質問し、具体的なイメージを持っておくと安心できるでしょう。雨の多い地域では特に重要な検討ポイントとなります。
屋根カバー工法はトベシンホームにご相談ください

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
| 本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
| 電話番号 | 0120-685-126 |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
トベシンホームは関東圏において、屋根工事の豊富な実績を持つ信頼の外装リフォーム専門店です。特に屋根カバー工法では、地域の気候特性を考慮した最適な工法と材料選びで、耐久性と美観を両立した施工を提供しています。
雨天時の屋根工事においても、適切な判断と対策で安全かつ高品質な施工を実現。経験豊富な自社スタッフが調査から施工、アフターフォローまで一貫して担当する体制により、お客様の不安を解消します。
また、補助金活用のサポートも行っており、申請手続きから施工までトータルにバックアップ。千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、雨対策が万全な屋根カバー工法をお考えの方は、まずは無料点検と最短即日の現地調査をトベシンホームにお任せください。

まとめ
屋根カバー工法は雨の日の施工において、工程によって施工可否が分かれます。足場設置や屋内準備作業は軽い雨でも可能ですが、防水シート設置や屋根材固定は晴れた日に行うべきでしょう。
雨天時の施工には作業員の安全面のリスクや防水性能への影響、工期遅延の可能性などの課題があります。特に金属屋根は雨で滑りやすくなるため、安全確保が最優先です。
カバー工法は葺き替え工法に比べて雨天時の住宅保護という点でメリットがありますが、どちらの工法でも雨対策は欠かせません。防水シートによる養生や段階的な施工計画、天気予報を活用した工期調整などの対策が効果的です。
屋根工事は家の寿命を左右する重要な工事です。特に雨の多い時期に施工する場合は、経験豊富な業者選びと適切な工期設定で、安全かつ高品質な屋根を実現しましょう。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。