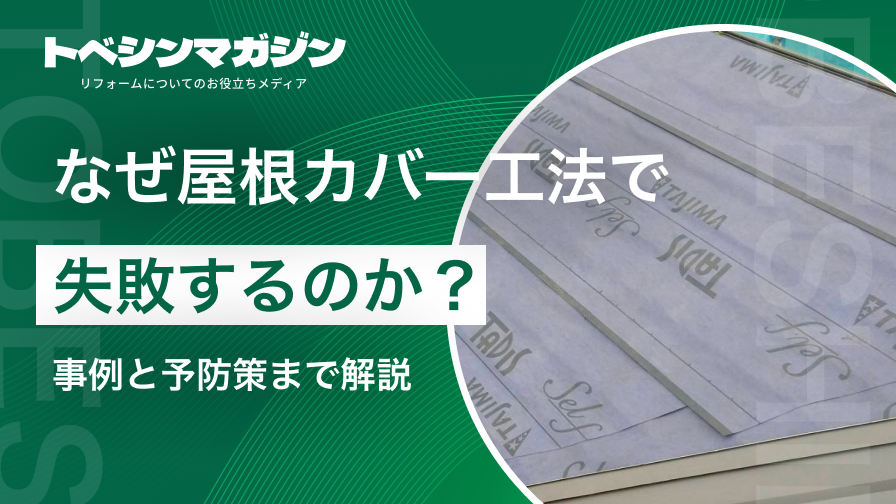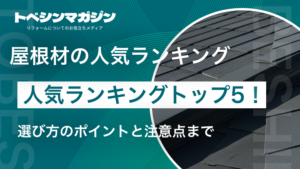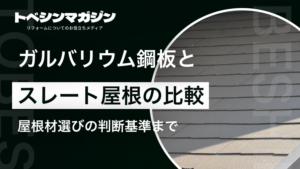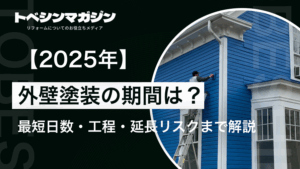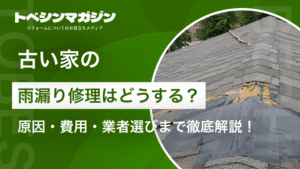「屋根カバー工法で失敗した話をよく聞くけど、本当なの?」
「業者がカバー工法を勧めてくるけど、リスクは大丈夫なのかな」
「失敗するとどんな問題が発生するの?」
近年、屋根リフォームで人気のカバー工法ですが、実は多くの失敗事例が報告されています。費用を抑えられる魅力的な工法である一方で、適切な条件や施工技術がなければ「はがれ」や「雨漏り」などの深刻なトラブルを招く可能性が高いのです。
とはいえ、すべての状況でカバー工法が不適切というわけではありません。条件に合った施工と適切な業者選びができれば、コスト面でも耐久性でも満足のいく結果を得られるでしょう。
この記事では、屋根カバー工法の失敗事例や原因、技術的に不適切な条件、そして失敗を防ぐための予防策と対応策まで詳しく解説します。
カバー工法を検討されている方は、後悔しない選択のためにぜひ参考にしてください。
また屋根カバー工法の全容については、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

この記事のポイント
- 主な失敗原因は不十分な事前調査の場合が多い
- 適切な下地調査が成功の鍵となる
- 高品質な防水シートの選択が重要
- 施工実績豊富な業者選びが必須

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。
専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
屋根カバー工法の失敗事例
屋根カバー工法では、様々な失敗事例が報告されています。
特に多いのが以下の4つのケースです。こうした失敗を避けるためにも、事前にどのようなリスクがあるのか理解しておきましょう。
これらの失敗事例を知ることで、カバー工法を検討する際のチェックポイントが明確になるでしょう。
事例1:強風による屋根材の剥離
「50メートルの強風でも大丈夫です」と業者から説明を受けたにもかかわらず、台風で風速30メートル程度の強風により屋根材が大量に剥がれてしまうケースが報告されています。
特に高台や海沿いなど、風の影響を受けやすい立地では、この問題が発生しやすい傾向にあるのです。原因としては、下地の野地板が腐食していたにもかかわらず、そのまま新しい屋根材を固定したことが挙げられます。
腐食した野地板には釘やビスがしっかりと固定されないため、強風時に引き抜かれてしまうのです。また、固定する際に釘ではなくビスを使用することで耐風性が向上しますが、コスト削減のため釘で施工されるケースも少なくありません。
この事例では、工事前の下地調査が不十分だったことと、保証内容についての説明不足が問題でした。適切な下地調査と補修を行い、適切な固定具を選択することが重要といえるでしょう。
事例2:施工不良による雨漏り発生
カバー工法による最も多い失敗事例は雨漏りの発生です。ある家庭では、カバー工法施工から数ヶ月後に天井に染みが現れ始めました。調査のため屋根材を一部めくると、防水シートの下の野地板がすでに腐食していたことが判明したのです。
カバー工法を施工する前から微小な雨漏りがあったものの、それが見落とされてしまいました。新しい屋根材で覆われたことで発見が遅れ、野地板だけでなく屋根骨組みの木材まで腐食が広がってしまったのです。
この場合、二重になった屋根材をすべて撤去し、野地板と骨組みの一部までやり直す大規模な工事が必要となりました。結果的に、当初カバー工法で節約したつもりが、通常の葺き替え工事の2倍以上の費用がかかってしまいました。
事前の雨漏り調査と屋根裏検査を徹底していれば防げた失敗事例です。カバー工法では見えない部分の状態確認が極めて重要といえるでしょう。
事例3:下地固定不足による屋根材変形
施工後しばらくは問題なく見えたものの、時間の経過とともに屋根材がうねったり変形したりする事例も報告されています。これは下地固定が不十分な状態で施工された場合に発生しやすい問題です。
屋根カバー工法では、既存の屋根材の上に新しい屋根材を取り付けるため、下地との固定に特に注意が必要となります。下地への固定が適切に行われていないと、温度変化による屋根材の膨張・収縮により徐々に変形が生じていくのです。
ある事例では、2年後に屋根全体がうねり、見た目の問題だけでなく、雨水が溜まる箇所ができて二次的な雨漏りが発生しました。原因を調査したところ、固定するビスの数が不足していたうえ、打ち込み位置も不適切だったことが判明したのです。
このようなケースでは、結局屋根材を全て撤去して再施工することになり、追加費用が必要となりました。施工業者の技術力と固定方法の確認が重要なポイントといえるでしょう。
事例4:防水シートの施工ミス
防水シートの施工ミスは、カバー工法の失敗の中でも特に深刻な問題を引き起こします。ある事例では、施工後の最初の雨で雨漏りが発生し、調査の結果、防水シートの重ね部分が不足していたことが原因と判明しました。
防水シートは通常、上から下へと重ねて雨水が下に流れるよう施工しますが、重ね幅が不足していたり、逆向きに施工されていたりすると、雨水が侵入してしまうのです。
また、谷部分や壁との取り合い部分など、複雑な形状の箇所で防水処理が不十分なケースも見られます。こうした箇所は防水性能が特に重要なため、施工ミスが直接雨漏りにつながりやすいのです。
防水シートの品質自体にも問題があるケースもあります。低品質な防水シートを使用した場合、10年ほどで劣化が始まり、その後の雨漏りの原因となることがあります。高品質な防水シート選びと適切な施工技術を持つ業者選定が重要といえるでしょう。
【時間軸別】屋根カバー工法で失敗する原因・問題
屋根カバー工法による失敗は、工事の時間軸によって大きく3つの段階に分けられます。
各段階で見落としやすいポイントや発生しやすい問題を理解することで、効果的に失敗を防ぐことが可能です。
それぞれの段階で注意すべきポイントを押さえておくことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
施工前に発生する失敗原因
カバー工法の失敗は、実は工事が始まる前の段階ですでに決まっていることが少なくありません。最も大きな原因は「不十分な事前調査」にあります。
特に野地板の状態確認が不足していると、後の大きなトラブルに直結します。腐食した野地板の上にカバー工法を施工すると、屋根材の固定力が不足し、強風で屋根材が飛散する危険性が高まるのです。
また、既存屋根の雨漏りの有無を見落とすケースも多く見られます。微小な雨漏りが進行している状態でカバー工法を行うと、問題が覆い隠されるだけでなく、発見が遅れることでさらに被害が拡大してしまいます。
住宅の構造条件の確認不足も重要な失敗原因です。屋根勾配が2.5寸未満の低勾配屋根に横葺きタイプの金属屋根を施工すると、雨水が逆流して雨漏りを引き起こす可能性があります。
こうした施工前の調査不足や条件確認の怠りが、後の深刻なトラブルを招く大きな要因となっているのです。
施工中に起こる技術的ミス
施工中に起こる技術的ミスは、職人の技術不足や施工方法の誤りから生じることが多いです。まず挙げられるのが「防水シートの不適切な施工」です。
防水シートは下から上ではなく、上から下へと重ねて雨水が流れるように施工する必要があります。この基本を無視した施工や、重ね代が不足している場合、雨水の侵入経路となってしまいます。
また、屋根材の固定方法にも注意が必要です。釘やビスの打ち込み位置が不適切だったり、数が足りなかったりすると、屋根材の固定力が低下します。特に強風地域では、ビスの使用と適切な打ち込み位置が重要なポイントとなるのです。
水切り板金や谷部分などの複雑な形状を持つ箇所の施工ミスも多く見られます。これらの部位は雨水が集中しやすく、わずかな施工不良が雨漏りの原因となります。
さらに、断熱材や通気層の確保が不十分だと、屋根内部での結露発生リスクが高まり、長期的な劣化を引き起こす可能性があるでしょう。
施工直後に判明する問題
カバー工法の施工直後に判明する問題は、早期発見できれば対応可能なケースも多いです。初期段階で最も多いのが「雨漏り」の発見でしょう。
施工直後に発生する雨漏りは、主に水切り部分や貫通部(煙突、換気扇など)の周辺から生じることが多いです。これらの部位は複雑な防水処理が必要となるため、施工ミスが起きやすい箇所となっています。
また、強い雨音の発生も施工直後によく指摘される問題です。特に金属屋根材を使用したカバー工法では、防音対策が不十分だと雨音が増幅されることがあります。これは施工前に説明がなかった場合、住民にとって大きな不満となるでしょう。
屋根材の浮きや歪みも施工直後に発見されることがあります。これは屋根材の固定が不十分だったり、下地の凹凸に合わせた調整が適切でなかったりする場合に生じます。
さらに、谷樋や軒樋の排水不良により、雨水が適切に流れずに溜まってしまうケースも少なくありません。こうした問題は施工直後の初回降雨時に発見されることが多いのです。
屋根カバー工法の後悔について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。

屋根カバー工法の失敗を防ぐ予防策
屋根カバー工法での失敗を防ぐためには、事前の準備と適切な判断が重要です。特に以下の3つの予防策は、トラブルを未然に防ぐための重要なポイントとなります。
これらの予防策を実行することで、カバー工法による失敗リスクを大幅に軽減できるでしょう。
予防策1:屋根裏からの調査を実施
カバー工法の成否を左右するのは、下地の状態です。屋根裏からの調査では、野地板の状態を直接確認します。健全な野地板は乾燥して固い状態を保っているはずです。
調査時にはシミや湿りがないか、指で押して柔らかくなっていないかをチェックしましょう。腐食が進んだ野地板はスポンジのような感触になり、釘やビスの効きも悪くなります。
また、小屋裏の湿気状態も重要なポイントです。湿気が多い場合は、雨漏りや結露が発生している可能性があります。野地板の劣化が見つかった場合は、カバー工法の前に必ず補修か交換を行う必要があるでしょう。
予防策2:高品質な防水シートの選ぶ
屋根カバー工法における雨漏りを防ぐ最重要ポイントは、質の高い防水シートの選択です。一般的なアスファルトルーフィングより、改質アスファルトルーフィング(通称ゴムアス)が適しています。
特に重要なのは「釘穴シール性」です。カバー工法では防水シートに多数の釘やビスが打ち込まれるため、これらの穴から雨水が侵入しない自己シール機能を持つ製品を選びましょう。
防水シートの厚みも重要で、1mm以上あるものが耐久性に優れています。業者に防水シートの種類や品質について詳しい説明を求め、雨漏りに対する保証があるかも確認するとよいでしょう。
予防策3:施工実績豊富な業者に依頼しよう
カバー工法の成功のカギは、業者選びにあります。まず確認すべきは「板金工事の専門性」です。カバー工法で使用される金属屋根材は、専門的な知識と技術を持つ板金工事会社が施工するのが最適です。
次に「施工実績」をチェックしましょう。会社の設立年数が長く、カバー工法の施工実績が豊富であれば、様々な状況に対応できる技術力を持っていると判断できます。
見積書の内容も重要です。工事内容が詳細に記載されているか、使用する材料の詳細や下地補修の有無などが明記されているかを確認しましょう。また、保証内容や期間についても必ず確認するべきです。
信頼できる屋根カバー工法業者の見分け方と探し方について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。

屋根カバー工法で失敗した場合の対応策
屋根カバー工法で問題が発生した場合の適切な対応策を知っておくことで、被害の拡大を防ぎ、適切な解決に向けて進めることができます。以下の3つの対応策について詳しく解説します。
問題発生時は冷静に状況を判断し、適切な対応を取ることが重要です。
対策方法1:専門業者による緊急点検と応急処置
屋根カバー工法で問題が発生したら、まず専門業者による緊急点検を依頼しましょう。特に雨漏りの場合は、迅速な対応が建物へのダメージを最小限に抑える鍵となります。
可能であれば施工業者に連絡するのが望ましいですが、対応が遅い場合は別の専門業者に依頼することも検討すべきです。緊急時には多くの屋根修理業者が即日対応を行っています。
緊急点検では問題の範囲と原因を特定します。応急処置としては、ブルーシートでの養生や部分的な防水テープ施工、屋内側での雨水受け皿設置などが一般的です。
緊急対応後は詳細な調査と見積りを依頼し、適切な修復方法を検討しましょう。記録写真や見積書は保管しておくことをお勧めします。
対策方法2:保証・保険適用の確認と申請手続き
経済的負担を軽減するためには、保証や保険の適用を確認することが重要です。まずは施工業者による工事保証の有無と範囲を確認しましょう。
施工不良による雨漏りや屋根材のはがれは保証対象となることが多いですが、自然災害による損害は免責となっているケースもあります。保証が適用される場合は、速やかに連絡して申請手続きを行いましょう。
施工業者の保証が適用されない場合は、火災保険の適用を検討します。近年の火災保険は火災だけでなく、風災・雪災・水災などの自然災害による損害もカバーしています。
保険申請には詳細な被害状況の写真や修理見積書が必要となるため、これらの資料を準備しておくことが大切です。専門的な知識を持つ業者のサポートを受けることも有効でしょう。
対策方法3:第三者機関による調査と再工事の検討
施工業者との交渉が難航する場合は、第三者機関による中立的な調査を依頼することが有効です。住宅リフォーム・紛争処理支援センターや建築士事務所協会などが対応しています。
特に「住まいるダイヤル」(0570-016-100)は、住宅リフォームのトラブルに関する相談窓口として利用できます。専門家による調査結果に基づいて、再工事の必要性や範囲を検討しましょう。
再工事を行う場合は、前回の失敗を繰り返さないよう、適切な工法と信頼できる業者を選定することが重要です。複数の業者から見積もりを取り、工事内容や使用材料、保証内容を比較検討するとよいでしょう。
費用負担については、原因と責任の所在に応じて施工業者との交渉が必要です。交渉が難航する場合は法的手段も検討すべきでしょう。
屋根カバー工法なら実績豊富のトベシンホームにご相談ください

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
| 本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
| 電話番号 | 0120-685-126 |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
トベシンホームは、千葉県・埼玉県・茨城県を中心に活動する外装リフォーム専門店です。屋根カバー工法においては、地域特有の気候条件や建築様式に精通したプロフェッショナルが、お客様の屋根の状態を適切に診断いたします。
当社では屋根カバー工法の重要ポイントである「下地調査」を徹底し、「はがれ」や「雨漏り」などのトラブルを未然に防ぐための提案を行っています。品質の高い防水シートと適切な屋根材を使用することで、長期間にわたって安心できる屋根をご提供するよう心がけています。
調査から施工、アフターフォローまで一貫して自社スタッフが担当するため、高品質な施工と適正価格を実現しております。また、補助金活用のサポートも行い、お客様の負担軽減にも努めています。
屋根カバー工法の適否判断や最適な工法選択でお悩みの際は、トベシンホームの無料点検をぜひご利用ください。最短即日での現地調査も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ
屋根カバー工法は、費用を抑えて短期間で工事を完了できる魅力的な選択肢ですが、適切な条件と施工技術が伴わなければ深刻なトラブルを招く可能性があります。
本記事では、強風による屋根材の剥離や雨漏り、下地固定不足による変形など、実際の失敗事例を紹介しました。
これらの失敗は主に施工前の不十分な調査や、施工中の技術的ミス、不適切な材料選択に起因することが明らかになっています。
失敗を防ぐためには、屋根裏からの詳細な下地調査、高品質な防水シートの選択、施工実績豊富な信頼できる業者への依頼が重要です。
そして万が一問題が発生した場合は、専門業者による緊急点検と応急処置、保証・保険適用の確認、必要に応じた第三者機関による調査などの対応策を講じるべきでしょう。
屋根カバー工法の採用を検討される際は、まず自宅の条件が適しているかを専門家に確認し、信頼できる業者選びを慎重に行うことで、トラブルのない快適な住環境を維持できます。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。