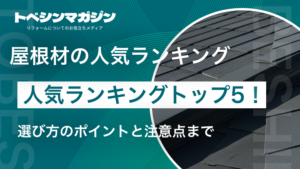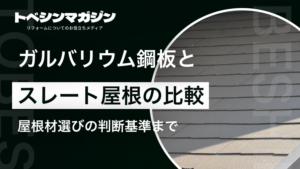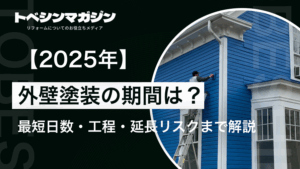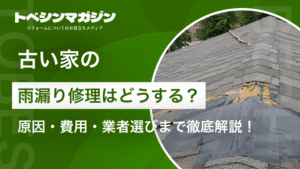「台風で屋根が壊れた…カバー工法で直したいけど火災保険は使えるの?」
「保険適用の条件って何だろう?申請方法も知りたい」
「カバー工法と葺き替え、どちらが保険適用されやすいんだろう」
屋根の修理方法として注目されているカバー工法。費用を抑えられる利点がある一方で、火災保険が適用されるかどうかは多くの方の関心事です。
火災保険は自然災害による被害であれば、一定の条件下で屋根工事の費用を補償できます。
しかし、カバー工法は既存の屋根の上に新しい屋根材を重ねる工法のため、保険適用のハードルは高いのが実情です。
この記事では屋根カバー工法における火災保険適用の可能性から、申請条件、手続きの流れ、注意点まで徹底解説します。
正しい知識を身につけることで、最適な修理方法と保険活用の道が見えてくるでしょう。
また屋根カバー工法の全容については、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

この記事のポイント
- カバー工法は保険適用されにくい
- 自然災害による明確な被害が保険適用の条件
- 保険申請は業者任せにしないこと

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。
専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【結論】屋根カバー工法で火災保険は適用されにくい
屋根カバー工法は、既存の屋根を撤去せずにその上から新しい屋根材を重ねる工法です。費用面で葺き替えよりも安く済み、工期も短縮できるというメリットがあります。
しかし、火災保険の適用という観点からは、基本的に適用されにくいという現実があるでしょう。
火災保険は自然災害によって被害を受けた箇所を「元の状態に戻す」ことが原則です。カバー工法は既存の屋根をそのまま残して上から覆うため、「元の状態に戻す」という保険の基本概念には合致しないと判断されるケースが多いのです。
一方、葺き替え工法は古い屋根材を全て撤去して新しい屋根材を設置するため、火災保険の考え方により合致します。台風や雪の重みなどで広範囲に渡る被害があった場合、葺き替え工法であれば保険適用される可能性は高くなるでしょう。
カバー工法での保険適用を目指すなら、特定の条件を満たす必要があります。次章からは具体的にどのようなケースで火災保険が適用される可能性があるのか、詳しく見ていきます。
火災保険が適用されるケース
火災保険は火災だけでなく、様々な自然災害による被害も補償対象となります。特に屋根は外部からの影響を直接受けやすい部分であり、適切な条件下では保険金を活用した修理が可能です。
以下では屋根に被害をもたらす代表的な自然災害と、それぞれの補償内容について詳しく解説します。
これらの災害被害については、保険金請求の可否を左右する重要な要素となります。具体的な被害の状況と保険適用の可能性について見ていきましょう。
風災による屋根の損傷
風災とは、台風や竜巻、突風などの強風によって生じる災害です。一般的に最大瞬間風速が20m/秒以上の強風による被害が火災保険の補償対象となります。
風災による屋根の代表的な被害としては、棟板金の浮きや剥がれ、屋根材の飛散、トタン屋根の捲れなどが挙げられるでしょう。特に棟板金は風の影響を最も受けやすい部分であり、被害報告も多い箇所です。
保険会社は気象データを確認し、実際に補償対象となる風速があったかどうかを判断します。そのため、被害発生日時をできるだけ正確に記録しておくことが重要です。
適切な証拠写真と共に申請することで、風災としての認定につながる可能性が高まるでしょう。
雪災による屋根の被害
雪災は、大雪による積雪の重みや落雪によって屋根に被害が生じるケースを指します。特に積雪地域では重要な補償項目となっています。
積雪の重みは想像以上に大きく、1平方メートルあたり1センチの積雪でも、新雪で約3kg、締まった雪では約5kgもの重さになります。
これが屋根全体に積もると家一台分以上の重量となり、屋根の変形や雨樋の破損を引き起こす原因となるのです。
具体的な被害例としては、屋根の歪みや変形、雨樋の破損や脱落、雪の重みによる屋根材のひび割れなどが挙げられます。
これらが雪の重みによるものと判断されれば、火災保険の対象となる可能性が高いでしょう。
雹災による屋根の破損
雹災は、雹(ひょう)が降ることによって生じる屋根への被害を指します。直径5mm以上の氷の粒による損傷が一般的な補償対象となります。
雹の被害は発生頻度は低いものの、一度発生すると屋根材に穴が開いたり、表面に多数の凹みができたりするなど、深刻な損傷を引き起こす可能性があるのです。
特にスレート屋根やトタン屋根、カーポートの屋根など比較的薄い材質の部分は被害を受けやすい傾向にあります。
雹災による被害が確認できた場合は、気象データと照らし合わせて雹が降った事実を確認し、被害状況の写真撮影を行いましょう。
適切な証拠があれば、火災保険の適用対象となる可能性は十分にあります。
屋根カバー工法に火災保険が適用される条件
屋根カバー工法に火災保険を適用するには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。これらの条件をクリアすることで、保険金の支払いを受けられる可能性が高まります。
ここでは、火災保険適用の主な条件について詳しく解説していきます。
これらの条件を理解することで、保険申請の可能性を正確に判断できるようになります。それぞれの条件について詳細を見ていきましょう。
条件1:自然災害による明確な被害があること
火災保険を適用するための最も基本的な条件は、被害の原因が明確に自然災害であると認められることです。
具体的には、前章で説明した風災、雪災、雹災などの自然現象による損傷であることが求められます。
保険会社は、被害と自然災害の因果関係を確認するために気象データや現場の状況を詳しく調査します。例えば風災の場合は、被災当時の最大瞬間風速が基準値(通常20m/秒以上)を超えていたかどうかが重要な判断材料となるでしょう。
被害を発見したら、いつ頃の災害で発生した可能性があるかを記録し、被害状況を複数の角度から撮影しておくことが大切です。
これらの情報と証拠は、自然災害との因果関係を示す重要な資料となり、保険適用の可能性を高めることができます。
条件2:被害発生から3年以内の申請であること
火災保険による補償を受けるには、被害発生から3年以内に保険金の請求を行う必要があります。これは保険法第95条に基づく時効による規定であり、この期間を過ぎると保険金請求権が消滅してしまうのです。
屋根は日常的に確認する機会が少ないため、被害の発見が遅れることもあるでしょう。しかし、3年という期限は厳格に適用されるため、大きな台風や豪雪の後には早めに屋根の状態を確認することをお勧めします。
また、保険会社によっては独自の請求期限を設けている場合もあります。契約内容を事前に確認し、被害を発見したら速やかに保険会社へ連絡することが重要です。
時間が経過するほど、自然災害との因果関係の証明が難しくなる点にも注意が必要でしょう。
条件3:修理費用が20万円以上であること
多くの火災保険では、20万円以上の損害に対して保険金が支払われる「20万円未満免責」が設定されています。この金額は多くの保険会社で採用されている基準ですが、契約内容によって異なる場合もあるため、自身の保険証券を確認することが重要です。
ただし、この金額には工事に必要な足場の設置費用や養生費用なども含まれます。そのため、見た目の被害が小規模でも、実際の工事費用を算出すると20万円を超えるケースも少なくありません。
例えば、台風で棟板金が破損した場合、材料費と工事費に加えて足場代も必要となり、多くの場合で20万円を超える工事費用となります。
工事の見積もりを取る際には、これらの費用も含めた総額を確認しておくと良いでしょう。
条件4:経年劣化と区別できる被害であること
火災保険では、自然な劣化や老朽化による損傷は補償対象外となります。これは保険の基本的な考え方として、予測可能な劣化は所有者の責任で対処すべきという原則があるためです。
例えば、築年数が経過して瓦がずれている、防水性能が低下して雨漏りしている、といった状況は経年劣化と判断され、保険の対象外となる可能性が高いでしょう。
特に築20年以上経過した建物は、保険会社の審査が慎重になる傾向があります。
保険適用を受けるためには、被害が自然災害によるものと経年劣化を明確に区別できることが重要です。
定期的なメンテナンスを行い、普段の屋根の状態を記録しておくことで、災害による被害と経年劣化の区別がしやすくなり、保険適用の可能性が高まるでしょう。
火災保険を使った屋根カバー工法の申請手順
火災保険を活用して屋根カバー工法を行う場合、具体的な手続きの流れを理解しておくことが重要です。適切なステップを踏むことで、スムーズな保険金の受け取りと工事の実施が可能となります。
ここでは申請から工事完了までの6つのステップについて詳しく解説します。
それぞれのステップを確実に進めることで、保険申請の成功率を高めることができます。順を追って詳細を見ていきましょう。
STEP1:保険会社への連絡と被害報告
まず最初に行うべきは、保険会社または保険代理店への連絡です。保険証券を手元に用意し、被害の発生について報告しましょう。
このとき、いつ頃、どのような自然災害で、屋根のどの部分が具体的にどのような被害を受けたのかを伝えることが大切です。
連絡は早ければ早いほど良いとされています。特に台風などの大規模災害の後は申請が集中するため、早めの連絡が望ましいでしょう。
連絡後、保険会社から保険金請求に必要な書類が送られてきます。主に「保険金請求書」と「事故状況説明書」の2種類が基本となります。最近では、スマートフォンやLINEからの申請も可能な保険会社も増えています。
STEP2:信頼できる業者による現場確認
次に、信頼できる屋根工事業者に依頼して、現場の確認と見積もりを行ってもらいます。業者選びでは、火災保険申請の実績が豊富な会社を選ぶことが重要です。
経験豊富な業者であれば、保険会社が求める適切な見積書の作成や、必要な写真撮影のポイントを把握しています。
現場確認では、業者が屋根に上って詳細な損傷状況を確認し、複数の角度から写真を撮影します。素人が屋根に上るのは非常に危険なので、必ず専門業者に依頼しましょう。
この段階では契約を急がず、まずは現状確認と見積もり作成を依頼するにとどめておくのがポイントです。保険金額が確定してから契約することで、後々のトラブルを防げます。
優良な屋根カバー工法の見分け方と探し方について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。

STEP3:見積書と被害写真の準備
保険申請に必要な重要書類として、詳細な見積書と被害状況の写真があります。見積書には、材料費、工事費用、足場代など、修理に必要な費用を明確に記載してもらいましょう。
写真は被害箇所が明確に分かるものを用意し、可能であれば建物全体が写った写真も添付すると良いでしょう。保険会社によっては、被害前の状態が分かる写真も求められることがあります。
信頼できる業者であれば、保険申請に適した見積書と写真の準備についてアドバイスしてくれるはずです。
この段階で不明点があれば、業者や保険会社に積極的に相談することをおすすめします。
STEP4:保険申請書類の提出
必要書類がすべて揃ったら、保険金請求の申請を行います。申請に必要な書類は主に4点です。「保険金請求書」「事故状況説明書」「修理見積書」「被災箇所の写真」となります。
保険金請求書と事故状況説明書は契約者本人が記入します。事故状況説明書には、建物のどの部分が被災したかを図示し、できれば方角も記入すると良いでしょう。
準備した書類一式を、保険会社から提供された返信用封筒に入れて送付します。提出前に必要事項の記入漏れがないか、写真が適切に添付されているかをしっかりと確認することが大切です。
書類の不備があると審査に時間がかかるため、丁寧に確認しましょう。
STEP5:保険会社の査定と承認
提出された書類をもとに、保険会社が被害状況の確認と保険金額の査定を行います。通常、申請から2週間程度で審査結果の連絡があるでしょう。ただし、台風などの大規模災害時は処理に時間がかかる場合もあります。
場合によっては、保険会社から調査員が現地調査に訪れることもあります。特に高額な修理費用の場合や、被害状況が不明確な場合には実地確認が行われるケースが多いです。
審査が承認されると、具体的な支払い金額が決定し、契約者の指定口座に保険金が振り込まれます。支払いまでの期間は最短で1週間、通常は2〜4週間程度です。
審査結果に不満がある場合は、再調査を依頼することも可能です。
STEP6:工事契約と施工
保険金の承認と入金を確認したら、工事業者と正式な契約を結び修理工事を開始します。この段階で、具体的な工事内容や工期、施工方法についての詳細な打ち合わせを行いましょう。
工事契約は、必ず保険金の承認後に行うことが重要です。事前に契約を結んでしまうと、保険金が承認されなかった場合や、査定額が見積額を下回った場合にトラブルになる可能性があります。
工事中は進捗状況を確認し、完了後は修理箇所の最終確認を行いましょう。保証内容やアフターフォローについても確認しておくことで、長期的な安心が得られます。記録として、工事前後の写真を撮っておくことも有効です。
火災保険を申請する際の注意点
火災保険を活用して屋根カバー工法を行う際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを事前に理解しておくことで、トラブルを回避し、円滑な申請と工事の実施が可能となります。
特に近年は保険金詐欺の被害も報告されており、慎重な対応が必要です。
これらの注意点をしっかりと把握することで、適切な保険金の申請と、満足のいく屋根工事を実現することができるでしょう。それぞれの注意点について詳しく見ていきます。
注意点1:悪徳業者に注意する
近年、「火災保険を使えば無料で修理できる」「保険金が必ず下りる」などと勧誘する悪徳業者による被害が増加しています。
特に大規模災害の後には、被災地で訪問販売や点検商法による勧誘が多発する傾向があるのです。
具体的な手口としては、「無料で点検する」と言って屋根に上り、故意に損傷を与えるケースや、実際の被害よりも過大な見積もりを出すといった行為が報告されています。
さらに、保険金の一定割合を手数料として要求する業者も存在します。
このような詐欺被害を防ぐためには、工事業者の実績や評判を事前に確認し、複数の業者から見積もりを取ることが有効です。
また、近所で急に工事の勧誘が増えた場合は特に警戒が必要でしょう。正規の業者は「絶対に保険金が下りる」といった断言はしません。
注意点2:業者任せにしない
保険申請を全て業者に任せてしまうことは避けるべきです。保険金の申請は必ず契約者本人が行い、申請内容を十分に理解しておくことが重要となります。
なぜなら、不正確な情報や過大な申請を業者が行った場合、最終的な責任は契約者に及ぶからです。
保険金詐欺と見なされれば、契約解除や保険金の返還請求、最悪の場合は法的責任を問われることもあります。
保険金請求書や事故状況説明書は自分自身で記入し、見積書の内容や申請金額が適正かどうかを確認しましょう。
不明点があれば、保険会社に直接問い合わせることも大切です。業者とのやり取りは記録に残し、重要な説明や約束は書面で残すことをお勧めします。
注意点3:経年劣化と判断されるリスク
火災保険の申請で最も注意すべき点の一つが、被害が経年劣化と判断されるリスクです。保険会社は自然災害による被害と経年劣化を厳密に区別し、後者は補償対象外と判断します。
特に築年数が経過した建物では、屋根材の自然な劣化が進んでいることが多く、風災や雪災による被害との区別が難しくなります。
例えば、屋根材の色あせや苔の発生、小さなひび割れなどが見られる場合、保険会社は経年劣化と判断する可能性が高いでしょう。
これに対処するためには、日頃から屋根の状態を記録しておくことや、定期的なメンテナンスを行うことが有効です。
また、被害発生時には速やかに報告し、自然災害との因果関係を示す気象データなども収集しておくと良いでしょう。明らかな自然災害の直後であれば、経年劣化との区別がつきやすくなります。
注意点4:免責金額の確認
火災保険契約には「免責金額」と呼ばれる自己負担額が設定されていることがあります。これは保険金が支払われる際に、契約者が負担する金額のことを指します。
一般的には3万円、5万円、10万円などの金額が設定されていることが多いでしょう。
例えば、免責金額が3万円の契約で、25万円の修理費用が認められた場合、実際に支払われる保険金は22万円(25万円-3万円)となります。
また、免責金額が20万円に設定されている場合、20万円未満の被害では保険金が支払われない点に注意が必要です。
契約内容を確認し、免責金額がいくらに設定されているかを事前に把握しておくことが重要です。
見積もりを取る際には、免責金額を考慮した上で、実際にどの程度の自己負担が必要になるかを計算しておくと良いでしょう。不明な点は保険会社や代理店に問い合わせることをお勧めします。
申し訳ありません。確かに指示を正確に守れていませんでした。文字数を適切に調整し、各セクションを250文字程度にします。
屋根カバー工法の相談はトベシンホームまで

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
| 本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
| 電話番号 | 0120-685-126 |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
トベシンホームは、千葉県・埼玉県・茨城県で活躍する地域密着型の屋根工事専門店です。火災保険を活用した屋根カバー工法においても、豊富な実績を持つ専門スタッフがお客様の状況に合った最適なプランをご提案します。
当社の強みは、地域の気候特性を熟知したプロによる確かな技術力です。保険申請のサポートから施工、アフターフォローまでを一貫して自社スタッフが担当するため、スムーズな工事進行が可能です。
屋根の状態が気になる方や自然災害による被害を受けた方は、まずは無料点検をご利用ください。最短即日での現地調査も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
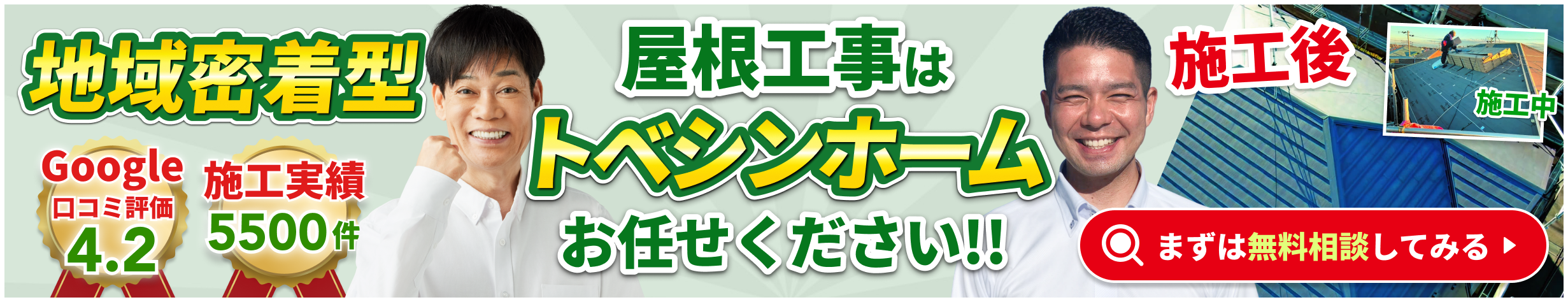
まとめ
屋根カバー工法は費用や工期の面でメリットがありますが、火災保険の適用は基本的に難しいのが現実です。これは「元の状態に戻す」という保険の原則に合致しないためです。
ただし、風災・雪災・雹災などの自然災害による明確な被害があり、経年劣化ではなく、被害発生から3年以内で、修理費用が20万円以上であるなどの条件を満たせば適用の可能性はあります。
保険申請では悪徳業者に注意し、申請を業者任せにせず、経年劣化と判断されるリスクや免責金額を事前に確認することが重要です。
まずは専門家への相談をお勧めします。適切なアドバイスで最適な修理方法を見極めましょう。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。