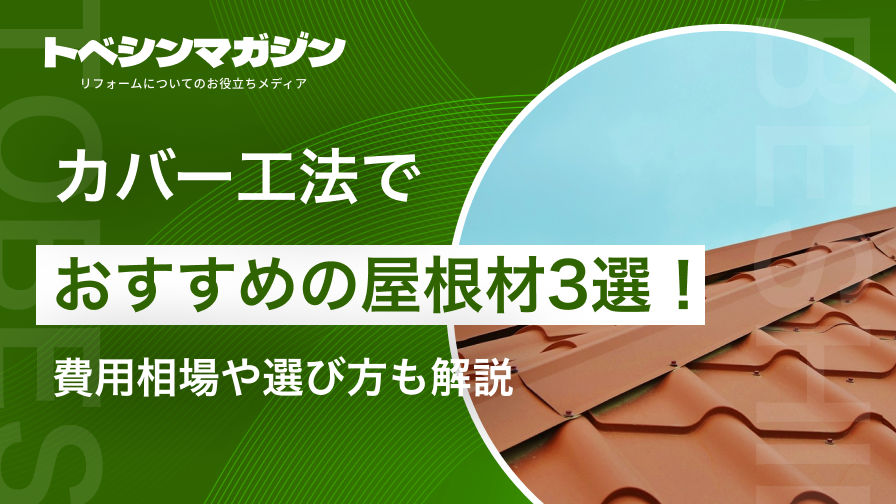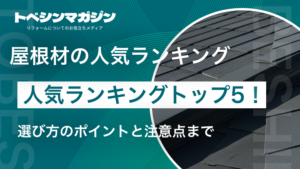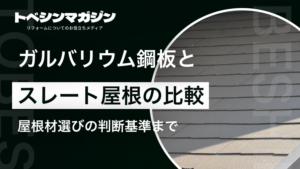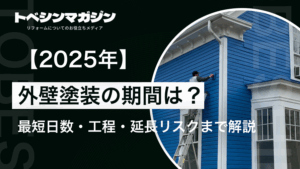「この屋根材で本当に大丈夫なのかな…」
「メーカーによって性能に違いはあるの?」
「耐久性と価格のバランスが取れた屋根材を選びたい」
カバー工法の屋根材選びで、このような悩みを抱える方は少なくないでしょう。とりわけ初めて検討する場合、数ある選択肢の中からどの屋根材を選べば良いのか判断に迷うものです。
実際、屋根材の選択を誤ると、耐用年数の違いによる予想外の費用負担や、早期劣化による雨漏りなど、様々なトラブルを引き起こす可能性があります。適切な屋根材を選ぶことは、長期的な住まいの快適性を左右する重要な決断といえるのです。
この記事では、カバー工法におすすめの屋根材3選から、メーカー別の特徴、費用相場、選び方のポイントまで詳しく解説していきます。
選ぶ際のポイントや事前に確認しておくべきことを把握することで、あなたの家に最適な屋根材を見つけることができるはずです。
また屋根カバー工法の全容については、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

この記事のポイント
- 屋根カバー工法におすすめの屋根材は3つ
- 材質・性能・保証内容の確認が重要
- カバー工法に不向きな屋根の状態がある

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。
専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
屋根カバー工法におすすめの屋根材3選
カバー工法で使用する屋根材には、耐久性と軽量性を兼ね備えた金属系の素材が適しています。以下、代表的な3つの屋根材について詳しく解説します。
それぞれの屋根材には特徴的な性能があり、建物の条件に応じて最適な選択が変わってきます。
ガルバリウム鋼板
金属屋根材の中でも最も一般的な屋根材で、カバー工法の定番として高い採用実績があります。1㎡あたりの重量が約5kgと非常に軽量なため、建物への負担が少ないのが特徴です。
防水性に優れ、雨漏りのリスクも低く抑えられます。耐用年数は30〜40年ほどで、費用は1㎡あたり6,000〜12,000円が一般的な相場となっています。
ただし、10〜15年ほどで塗装によるメンテナンスが必要です。海岸部など環境によっては錆びやすい傾向もあるため、定期的な点検と補修を心がける必要があるでしょう。
ガルバリウム鋼板の屋根カバー工法の費用相場や工事の流れについて、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。

ジンカリウム鋼板
表面をガラス質の特殊塗装で仕上げた高性能な屋根材で、色あせしにくい特徴があります。一般的なガルバリウム鋼板と異なり、塗装によるメンテナンスが不要な点が大きな魅力です。
断熱性能が高く、耐震性や防音性、防火性にも優れています。耐用年数は30〜50年と長く、費用は1㎡あたり8,000〜14,000円とやや高めですが、長期的な視点では維持費を抑えられる可能性があります。
特に海岸部など塩害の影響を受けやすい地域での採用がおすすめです。表面の特殊塗装により、厳しい環境下でも高い耐久性を発揮することができるでしょう。
SGL鋼板
次世代の屋根材として注目を集めており、耐食性は一般的なガルバリウム鋼板の約3倍とされています。30〜40年の耐用年数があり、遮熱性に優れた塗装により、室内への熱の伝わりも抑制できます。
赤さびは20年、穴あきは25年の保証が一般的で、安心して使用できる屋根材です。価格は1㎡あたり10,000〜15,000円と高めですが、高い耐久性と快適性を求める方に適した選択肢といえます。
特に厳しい気候条件下での使用や、長期的な資産価値の維持を重視する場合におすすめです。断熱材との相性も良く、夏場の冷房効率を高めることも可能です。
屋根カバー工法の費用相場
カバー工法の費用は、建物の条件や使用する材料によって変動します。工事費用と材料費に分けて、具体的な相場を解説します。
予算計画を立てる際の参考にしてください。
工事の費用相場
カバー工法の工事費用は、1㎡あたり8,000〜10,000円が一般的な相場です。
30坪程度の住宅の場合、屋根面積はおよそ100〜120㎡となるため、基本的な工事費用の目安を算出することができます。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 基本工事費 | 1㎡あたり8,000〜10,000円 |
| 足場代 | 15~20万円 |
| 防水シート | 1㎡あたり500~1,000円 |
| 棟板金施工 | 1メートルあたり2,500~6,000円 |
| 下地補修 | 1㎡あたり2,500~4,000円 |
屋根の形状が複雑な場合や建物の高さによって、足場代は変動する可能性があります。
ただし、葺き替え工事と比較すると、廃材処理費用が不要なため、総じて工事費用を抑えられる工法といえるでしょう。
屋根材の費用相場
屋根材の価格は素材によって異なります。一般的な相場は以下の通りです。
| 屋根材 | 価格(1㎡あたり) |
|---|---|
| ガルバリウム鋼板 | 6,000~12,000円 |
| ジンカリウム鋼板 | 8,000~14,000円 |
| SGL鋼板 | 10,000~15,000円 |
| 断熱材付き仕様 | +2,000~3,000円 |
| 遮熱性能強化仕様 | +3,000~5,000円 |
断熱材付きの屋根材や遮熱性能の高い屋根材を選択する場合は、追加費用が発生します。
ただし、これらの性能は光熱費の削減やより長い耐用年数につながるため、長期的な視点では投資価値の高い選択肢となるでしょう。
屋根カバー工法の屋根材選びのポイント
後悔しない屋根材選びのために、以下の3つのポイントを押さえておく必要があります。
それぞれのポイントについて詳しく解説していきましょう。
これらのポイントを確認することで、信頼性の高い屋根材を選べます。
ポイント1:材質の見極め
カバー工法で使用する屋根材は、軽量性と耐久性のバランスが重要です。重すぎると建物に負担がかかり、軽すぎると耐久性に問題が生じる可能性があるからです。
一般的な金属屋根材の場合、1㎡あたり5kg程度が目安です。これは従来の屋根材の1/10程度の重さで、建物への負担を最小限に抑えられます。
また、海岸部など環境による影響も考慮する必要があります。塩害の影響を受けやすい地域では、耐食性の高いジンカリウム鋼板やSGL鋼板の採用を検討するのが賢明です。
ポイント2:性能の確認
屋根材の性能は、断熱性・遮音性・耐風性の3つの観点から確認するのが基本です。特に断熱性は光熱費に直結するため、重要な判断基準となります。
断熱材付きの屋根材を選択すると、夏場の小屋裏温度は一般的な屋根材と比べて15℃程度低く抑えることができます。また、雨音が気になる場合は、遮音性の高い屋根材を選択することで、快適な室内環境を実現できるでしょう。
耐風性については、屋根材の固定方法も重要です。かん合式の固定方法を採用している屋根材は、強風に対する耐性が高いという特徴があります。
ポイント3:保証内容の確認
メーカーが提供する保証内容は、製品の信頼性を判断する重要な指標です。一般的な保証は穴あきや赤さびに対するものが基本ですが、その保証期間は製品によって大きく異なります。
良質な屋根材の場合、赤さびは20年、穴あきは25年程度の保証が標準的です。また、遮熱性能や色あせに対する保証が付帯している製品もあります。
ただし、保証を受けるためには定期的なメンテナンスが必要な場合も多いため、保証条件も併せて確認することが重要です。メーカーの保証と施工業者の保証、それぞれの範囲と期間を明確にしておきましょう。
屋根カバー工法に不向きな屋根の状態
屋根カバー工法は、既存の屋根の状態によって施工できない場合があります。
以下の3つの状態について、詳しく解説していきます。
これらの状態が確認された場合は、葺き替え工事など他の工事方法を検討する必要があります。
下地が腐食している
既存の屋根の下地が腐食している場合、その上から新しい屋根材を施工しても根本的な解決にはなりません。むしろ、問題を隠してしまうことで、より深刻な事態を招く可能性があります。
特に雨漏りの形跡がある箇所は、下地の腐食が進行している可能性が高いため、注意が必要です。このような状態でカバー工法を行うと、屋根材の固定強度が不足し、台風などで屋根材が飛散するリスクも高まるでしょう。
下地の腐食が見られる場合は、葺き替え工事による全面改修を検討することが賢明です。
野地板が劣化している
野地板は屋根材を支える土台となる重要な部材です。この野地板が劣化していると、新しい屋根材をしっかりと固定することができません。
特に築年数が古い建物や、過去に雨漏りがあった箇所は、野地板が脆くなっている可能性があります。このような状態では、釘やビスが効かず、屋根材の固定が不安定になってしまいます。
野地板の劣化が見られる場合は、まず野地板の交換を行う必要があり、カバー工法は適していません。
形状が不規則である
屋根の形状が不規則な場合、カバー工法による施工は困難です。特に和瓦のような凹凸のある屋根材の上からの施工は、防水性の確保が難しく、雨漏りのリスクが高まります。
また、複雑な形状の屋根では、屋根材の取り合い部分で隙間が生じやすく、そこから雨水が侵入する可能性があります。さらに、屋根材同士の接合部も多くなるため、経年劣化による不具合が発生しやすいです。
このような場合は、既存の屋根材を撤去して葺き替える方が、長期的な安全性を確保できます。
屋根材を選ぶ際に確認しておくべき3つの注意点
信頼性の高い屋根材を選ぶために、以下の3つの項目について確認することが重要です。
それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
これらの確認を怠ると、予期せぬトラブルの原因となります。
注意点1:強度を確認する
屋根材の強度は、耐風圧性能と衝撃強度の2つの観点から確認する必要があります。特に耐風圧性能は、台風が多い日本の気候では重要な判断基準となります。
横葺きタイプの屋根材は、縦葺きタイプと比べて約1.4倍の耐風性能があります。また、かん合式の取り付け方法を採用している屋根材は、より高い耐風性能を発揮できるでしょう。
衝撃強度については、屋根材の厚みと表面処理が関係します。特に積雪地域では、雪の重みに耐えられる強度を持った屋根材を選ぶ必要があります。
注意点2:保証範囲を確認する
メーカーが提供する保証は、製品によって大きく異なります。一般的な保証項目は「穴あき」「赤さび」「色あせ」の3つですが、その保証期間や条件は製品ごとに確認が必要です。
重要なのは、保証の対象となる不具合の範囲と、保証を受けるための条件です。定期的なメンテナンスが保証の条件となっている場合も多く、その費用も考慮に入れる必要があるでしょう。
また、メーカー保証と施工業者の工事保証は別物であることも理解しておく必要があります。両方の保証内容を確認しましょう。
注意点3:耐用年数を確認する
屋根材の耐用年数は、材質や表面処理によって20年から50年まで大きな幅があります。一般的な金属屋根材の場合、30〜40年程度の耐用年数が標準です。
ただし、これは適切なメンテナンスを行うことが前提となります。定期的な点検や必要に応じた補修を怠ると、耐用年数が大幅に短くなる可能性があります。
地域の気候条件も考慮に入れる必要があるでしょう。海岸部など厳しい環境では、より耐久性の高い屋根材を選択することが望ましいのです。
屋根カバー工法の耐用年数について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。

カバー工法のご相談はトベシンホームへ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
| 本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
| 電話番号 | 0120-685-126 |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
トベシンホームは、千葉県・埼玉県・茨城県で豊富な屋根工事実績を持つ、信頼の外装リフォーム専門店です。
各地域の気候特性や建築様式を熟知したプロフェッショナルが、お客様の建物に最適な屋根材と工事プランをご提案いたします。
当社では、事前調査から施工、アフターフォローまでを経験豊富な自社スタッフが一貫して担当しております。
これにより、高品質な施工と適正価格を実現しています。カバー工法に関する豊富な知識と施工実績を活かし、建物の状態や予算に応じた最適なプランをお届けします。
屋根材の選定でお悩みの方は、無料点検と最短即日での現地調査を承っておりますので、ぜひトベシンホームへご相談ください。

まとめ
カバー工法で使用する屋根材は、建物の状態や環境条件によって最適な選択肢が変わってきます。ガルバリウム鋼板、ジンカリウム鋼板、SGL鋼板など、それぞれの特徴を理解した上で選定することが重要です。
適切な屋根材を選ぶためには、材質の見極めから性能、保証内容まで、しっかりと確認することが大切です。また、既存の屋根の状態によってはカバー工法が適さないケースもあるため、事前の入念な調査も欠かせません。
信頼できる業者に相談し、建物の状態や予算に合った屋根材を選ぶことで、長く安心して使える屋根に仕上げることができるはずです。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。