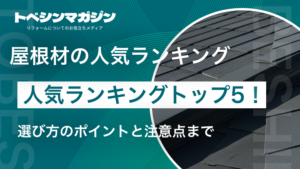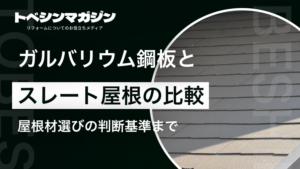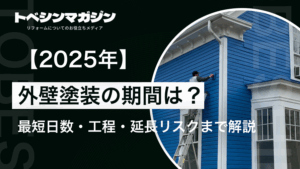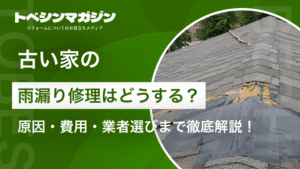「屋根カバー工法にすると家が重くなりすぎないかな?」
「地震が来たときに危なくないのだろうか」
「どれくらい重くなるのか知りたい」
屋根のリフォーム方法として人気のカバー工法。既存の屋根の上に新しい屋根材を重ねる工法なので、どうしても重量が増加します。そのため、建物への負担や耐震性について心配される方も多いでしょう。
カバー工法による重量増加は屋根材の組み合わせによって異なりますが、一般的な住宅であれば耐震性に大きな影響はありません。ただし、建物の状態によっては適さないケースもあるため、正しい知識を持って判断することが重要です。
この記事では、屋根カバー工法による重量増加の具体的な数値から、耐震性への影響、適さない条件まで詳しく解説します。屋根カバー工法を検討されている方はぜひ参考にして、安全かつ経済的な屋根リフォームの参考にしてください。
また屋根カバー工法の全容については、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

この記事のポイント
- 屋根カバー工法の重量増加は限定的
- 一般住宅では耐震性に問題は少ない
- 屋根カバー工法が適さない条件もあるので注意が必要

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。
専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
屋根カバー工法による重量増加とは?
屋根カバー工法とは、既存の屋根材を撤去せず、その上に新しい屋根材を重ねて施工する工法です。
工期の短縮やコスト削減というメリットがある一方で、屋根材が二重になるため重量が増加します。この重量増加が建物に与える影響について、正しく理解しておく必要があるでしょう。
重量増加については「どのくらい重くなるのか」という具体的な数値を知ることが、適切な判断をするための第一歩となります。
屋根材の種類や組み合わせによって増加する重量は異なるため、個々の状況に応じた検討が必要です。
屋根材別の基本重量
屋根材にはさまざまな種類があり、それぞれ重量が異なります。カバー工法を検討する際には、まず現在の屋根材と新しく施工する屋根材の重量を理解しておくことが重要です。
一般的な屋根材の1㎡あたりの重量は以下の通りです。
| 屋根材の種類 | 1㎡あたりの重量 |
|---|---|
| スレート屋根(コロニアル) | 約18〜21kg/㎡ |
| ガルバリウム鋼板 | 約5kg/㎡ |
| 石粒付き金属屋根 | 約7kg/㎡ |
| アスファルトシングル | 約9〜12kg/㎡ |
| トタン屋根 | 約3〜4kg/㎡ |
| セメント瓦 | 約42kg/㎡ |
| 粘土瓦(和瓦) | 約48kg/㎡ |
これに加えて、防水シート(ルーフィング)の重量も約1kg/㎡程度あります。カバー工法では新たに防水シートも施工するため、この重量も考慮する必要があるでしょう。
スレート屋根やトタン屋根の場合、比較的軽量なガルバリウム鋼板でカバー工法を施工することが多く、重量増加を最小限に抑えることが可能です。一方で、セメント瓦や粘土瓦は非常に重いため、カバー工法には適していません。
カバー工法後の総重量計算
カバー工法を施工した後の総重量は、既存の屋根材の重量に新しい屋根材と防水シートの重量を加えることで計算できます。一般的な住宅の例で見てみましょう。
例えば、100㎡のスレート屋根にガルバリウム鋼板と防水シートを施工した場合の総重量計算は以下の通りです。
| 項目 | 単位重量 | 面積 | 総重量 |
|---|---|---|---|
| 既存のスレート屋根 | 21kg/㎡ | 100㎡ | 2,100kg |
| 新しいガルバリウム鋼板 | 5kg/㎡ | 100㎡ | 500kg |
| 新しい防水シート | 1kg/㎡ | 100㎡ | 100kg |
| カバー工法後の総重量 | 2,700kg |
つまり、総重量は約600kg増加することになります。
重量増加率としては約30%となり、屋根全体で見ると決して無視できない重量ですが、住宅全体の重量から見ると一部分に過ぎません。
カバー工法による重量増加を具体的に把握することで、建物への影響を正確に評価できるようになるでしょう。適切な屋根材の選択と、建物の状態に合わせた施工方法の検討が重要です。
【屋根材別】屋根カバー工法による重量の変化
屋根カバー工法を実施する際、既存の屋根材と新しく施工する屋根材の組み合わせによって重量増加の度合いが変わります。どの組み合わせが最適なのかは、建物の構造や状態によって異なるため、代表的な組み合わせごとの重量変化を知っておくことが大切です。
ここでは、実際の数値を基に各組み合わせの重量変化を比較し、どのような影響があるのかを見ていきましょう。これらの情報を参考に、自宅の屋根に最適な選択ができるはずです。
スレート屋根にガルバリウム鋼板を施工した場合
スレート屋根にガルバリウム鋼板を施工するのは、最も一般的なカバー工法の組み合わせです。スレート屋根(コロニアル)は1㎡あたり約18〜21kgの重量があり、ガルバリウム鋼板は約5kg、防水シートは約1kgです。
100㎡の屋根面積を例にすると、カバー工法後の総重量は以下のようになります。
| 項目 | 単位重量 | 面積 | 総重量 |
|---|---|---|---|
| 既存のスレート屋根 | 20kg/㎡ | 100㎡ | 2,000kg |
| 新しいガルバリウム鋼板 | 5kg/㎡ | 100㎡ | 500kg |
| 新しい防水シート | 1kg/㎡ | 100㎡ | 100kg |
| カバー工法後の総重量 | 2,600kg |
増加する重量は約600kgで、これは既存屋根に対して約30%の増加率となります。この重量は小型自動車1台分程度で、一般的な住宅の構造ではほとんど問題になりません。
むしろガルバリウム鋼板の軽さが活かされた組み合わせといえるでしょう。
スレート屋根にアスファルトシングルを施工した場合
スレート屋根にアスファルトシングルを施工する場合、重量増加はガルバリウム鋼板よりもやや大きくなります。アスファルトシングルは1㎡あたり約9〜12kgと、ガルバリウム鋼板の約2倍の重量があるためです。
100㎡の屋根面積で計算すると、カバー工法後の総重量は以下のようになります。
| 項目 | 単位重量 | 面積 | 総重量 |
|---|---|---|---|
| 既存のスレート屋根 | 20kg/㎡ | 100㎡ | 2,000kg |
| 新しいアスファルトシングル | 12kg/㎡ | 100㎡ | 1,200kg |
| 新しい防水シート | 1kg/㎡ | 100㎡ | 100kg |
| カバー工法後の総重量 | 3,300kg |
増加する重量は約1,300kgで、既存屋根に対して約65%の増加率となります。
この重量増加は無視できるものではありませんが、一般的な日本の住宅は余裕を持って設計されているため、多くの場合問題はないとされています。
スレート屋根のカバー工法の費用相場や注意点について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。

トタン屋根にガルバリウム鋼板を施工した場合
トタン屋根にガルバリウム鋼板を施工する場合、重量増加はさらに少なくなります。
トタン屋根は1㎡あたり約3〜4kgと非常に軽量で、これにガルバリウム鋼板の約5kgと防水シートの約1kgを加えても、増加は限定的です。
100㎡の屋根面積で計算すると、カバー工法後の総重量は以下のようになります。
| 項目 | 単位重量 | 面積 | 総重量 |
|---|---|---|---|
| 既存のトタン屋根 | 4kg/㎡ | 100㎡ | 400kg |
| 新しいガルバリウム鋼板 | 5kg/㎡ | 100㎡ | 500kg |
| 新しい防水シート | 1kg/㎡ | 100㎡ | 100kg |
| カバー工法後の総重量 | 1,000kg |
増加する重量は約600kgですが、既存屋根に対する増加率は約150%と高くなります。
しかし、総重量自体はスレート屋根へのカバー工法と比べても半分以下であり、建物への負担は最小限に抑えられるでしょう。
ガルバリウム鋼板による屋根カバー工法の費用やメリットについて、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。

トタン屋根にアスファルトシングルを施工した場合
トタン屋根にアスファルトシングルを施工する場合、ガルバリウム鋼板よりも重量増加は大きくなります。トタン屋根の軽さとアスファルトシングルの重さの対比が顕著になる組み合わせです。
100㎡の屋根面積で計算すると、カバー工法後の総重量は以下のようになります。
| 項目 | 単位重量 | 面積 | 総重量 |
|---|---|---|---|
| 既存のトタン屋根 | 4kg/㎡ | 100㎡ | 400kg |
| 新しいアスファルトシングル | 12kg/㎡ | 100㎡ | 1,200kg |
| 新しい防水シート | 1kg/㎡ | 100㎡ | 100kg |
| カバー工法後の総重量 | 1,700kg |
増加する重量は約1,300kgで、既存屋根に対する増加率は約325%となります。この増加率は非常に高いものの、総重量自体はスレート屋根へのカバー工法よりも軽く、多くの一般的な住宅構造では問題なく対応できます。
ただし、建物の状態によっては慎重な判断が必要でしょう。
アスファルトシングルによる屋根カバー工法の特徴や費用について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。

屋根カバー工法の重量が耐震性に与える影響
屋根カバー工法を検討する際、多くの方が気にされるのが耐震性への影響です。
確かに屋根の重量が増えることで建物への負荷は大きくなりますが、その影響は一般的に考えられているほど深刻ではないケースが多いです。
ここでは、重量増加が耐震性にどのような影響を与えるのか詳しく見ていきましょう。
これらの知識を得ることで、屋根カバー工法による重量増加が本当に心配すべきものなのか、適切に判断できるようになるでしょう。
重量増加が耐震性に与える影響は限定的
結論から言うと、屋根カバー工法による重量増加は、一般的な住宅の耐震性に大きな影響を与えることはありません。
前述のとおり、スレート屋根にガルバリウム鋼板を施工した場合の重量増加は約600kg程度で、これは住宅全体の重量から見ればわずかな割合に過ぎないのです。
実際、日本家屋は瓦屋根のような重い屋根材にも対応できるよう設計されていることがほとんどです。
粘土瓦(和瓦)は1㎡あたり約48kgもあり、100㎡の屋根だと4,800kgにも達します。これと比較すると、カバー工法による重量増加は大幅に軽いことがわかるでしょう。
また、屋根カバー工法では軽量な屋根材を使用するケースが多く、最も一般的なガルバリウム鋼板は瓦の約1/10の重さしかありません。このように軽量な材料を選ぶことで、重量増加による影響を最小限に抑えることが可能です。
屋根カバー工法後の耐震評価点の変化
建物の耐震性能は「耐震評価点」という数値で表されることがあります。これは震度6強〜7程度の地震に対して、建物が倒壊する可能性を数値化したものです。
一般的に以下のような評価基準があります。
| 耐震評価点 | 判定評価 |
|---|---|
| 1.5以上 | 倒壊しない |
| 1.0以上1.5未満 | 倒壊する可能性が低い |
| 0.7以上1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
| 0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
カバー工法による重量増加は、この耐震評価点にどのような影響を与えるのでしょうか。耐震評価点は「必要耐力」に対する「保有耐力」の比率で計算されます。
必要耐力は建物の重量に比例するため、重量が増えると必要耐力も増加します。
しかし、通常の住宅では保有耐力に余裕があるため、カバー工法程度の重量増加では耐震評価点が1.0を下回るケースはほとんどありません。
ただし、もともと耐震性に問題がある建物では注意が必要です。
地震発生時の重量増加による建物への負荷
地震が発生した際、建物にかかる力は建物の重量に比例します。そのため、屋根が重くなると地震時の揺れによる負荷も大きくなります。
特に注意すべきは、重量増加によって建物の重心が上方に移動する点です。
建物の重心が高くなると、地震の揺れに対して不安定になりやすく、揺れが増幅される可能性があります。
しかし、カバー工法による重量増加は住宅全体から見れば限定的であり、重心位置に大きな変化をもたらすことはあまりありません。
特に、1981年以降の新耐震基準で建てられた住宅では、屋根カバー工法による重量増加が耐震性に与える影響は小さいと考えられています。
ただし、1981年以前の旧耐震基準の住宅や、築年数が長く構造体が劣化している場合には、事前に専門家による耐震診断を受けることをお勧めします。
屋根カバー工法が適さない条件
屋根カバー工法はコスト面や工期の短さなど多くのメリットがありますが、すべての建物に適しているわけではありません。
むしろ、特定の条件下では避けるべき工法といえるでしょう。そのような条件を理解しておくことで、後悔のない選択ができます。
これらの条件に当てはまる場合は、カバー工法ではなく葺き替え工事を検討することをお勧めします。安全性を最優先に考えることが大切です。
条件1:築年数が古く構造体が劣化している
築年数が古い建物、特に1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅では、屋根カバー工法による重量増加が耐震性に影響を与える可能性があります。
築30〜40年以上経過した建物では、柱や梁といった構造体が経年劣化していることも多く、追加の重量負荷に耐えられない場合があるのです。
旧耐震基準の建物は現代の建築基準と比較して耐震性が低く設計されています。そのため、カバー工法で屋根の重量が1.3〜1.6倍に増加すると、地震時の揺れが増幅される恐れがあります。
実際、耐震診断の結果、すでに耐震評価点が低い建物では、屋根の軽量化が推奨されることも多いでしょう。
このような状況では、既存の屋根材を撤去してから軽量な屋根材を設置する葺き替え工事の方が適しています。
もし屋根カバー工法を強く希望される場合は、事前に専門家による耐震診断を受け、必要に応じて耐震補強工事を行うことをお勧めします。
条件2:下地の野地板が傷んでいる
野地板とは屋根材を支える下地材のことで、この部分に劣化や腐食がある場合、屋根カバー工法は避けるべきです。
劣化した野地板の上にカバー工法を施工すると、新しい屋根材を固定するための釘やビスがしっかりと効かず、強風時に屋根材がはがれる危険性が高まります。
野地板の状態を確認するには、屋根裏からの調査が最も確実です。変色や腐食、たわみなどが見られる場合は劣化のサインと言えるでしょう。
また、屋根を歩いた際にふかふかと沈む感覚がある場合も、野地板の劣化を疑うべきです。
残念ながら、カバー工法を提案する業者の中には下地調査を十分に行わないケースもあります。見積もりの段階で屋根裏からの調査を行わない業者は、技術力や信頼性に疑問があると言えるでしょう。
下地の状態が確認できない、あるいは劣化が確認された場合は、必ず葺き替え工事を選択し、野地板から交換することをお勧めします。
条件3:既存の屋根が雨漏りしている
すでに雨漏りが発生している屋根に対しては、絶対にカバー工法を選択すべきではありません。雨漏りは建物の構造自体に悪影響を及ぼす深刻な問題で、カバー工法ではこの根本的な原因を解決できないのです。
雨漏りがあるということは、既に屋根のどこかに水の侵入経路が存在しており、野地板や屋根骨組みが湿気にさらされている可能性が高いでしょう。このような状態でカバー工法を施工すると、問題が覆い隠されるだけで根本的な解決にはなりません。
さらに、カバー工法により屋根が二重構造になることで、雨漏りの発見がますます遅れる可能性があります。
発見が遅れれば遅れるほど、腐食の範囲は広がり、修復に必要な費用は増大します。最悪の場合、建物の構造的な問題にまで発展する恐れもあるのです。
雨漏りの形跡がある場合は、必ず葺き替え工事を選択し、野地板まで露出させて問題箇所を特定・修復することが重要です。
条件4:建物の耐荷重に問題がある
建物の設計上の耐荷重に余裕がない場合、屋根カバー工法による重量増加は避けるべきです。
特に、過去の増改築によって構造が変更されていたり、設計当初から屋根の荷重ギリギリで設計されていたりする建物では注意が必要です。
また、特殊な構造の建物、例えば木造と鉄骨の混構造や、大きな吹き抜けがある住宅なども、一般的な木造住宅とは耐荷重条件が異なる場合があります。
このような建物では、カバー工法による重量増加が局所的な負担増につながり、予期せぬ問題を引き起こす可能性があるでしょう。
さらに、既存の屋根自体が重量のある屋根材(瓦屋根など)の場合も屋根カバー工法は適していません。和瓦は1㎡あたり約48kgもあり、その上に新たな屋根材を重ねることは、技術的にも構造的にも問題があるのです。
このような場合は、既存の重い屋根材を撤去し、軽量な屋根材に葺き替える工事が最適な選択となります。
屋根カバー工法の相談はトベシンホームまで

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
| 本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
| 電話番号 | 0120-685-126 |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
トベシンホームは、屋根カバー工法の施工実績が豊富な外装リフォーム専門店です。
関東エリア、特に千葉県・埼玉県・茨城県を中心に活動し、地域特有の気候条件や建築特性に精通したプロフェッショナルが、お客様の屋根の状態を適切に診断いたします。
当社では屋根カバー工法における重要ポイントである「下地調査」を特に重視しています。重量増加が建物に与える影響を正確に評価し、適切な屋根材の選定から施工まで一貫して対応。お客様の住宅に最適な提案をご提供します。
高品質な防水シートと軽量かつ耐久性に優れた屋根材を使用し、長期間安心できる屋根をご提供することがトベシンホームの強みです。
また、各種補助金の活用サポートも行っており、経済的な負担軽減にも貢献しています。
屋根カバー工法が本当にご自宅に適しているのか、重量面での不安はないか、まずはトベシンホームの無料点検をご利用ください。
最短即日での現地調査も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
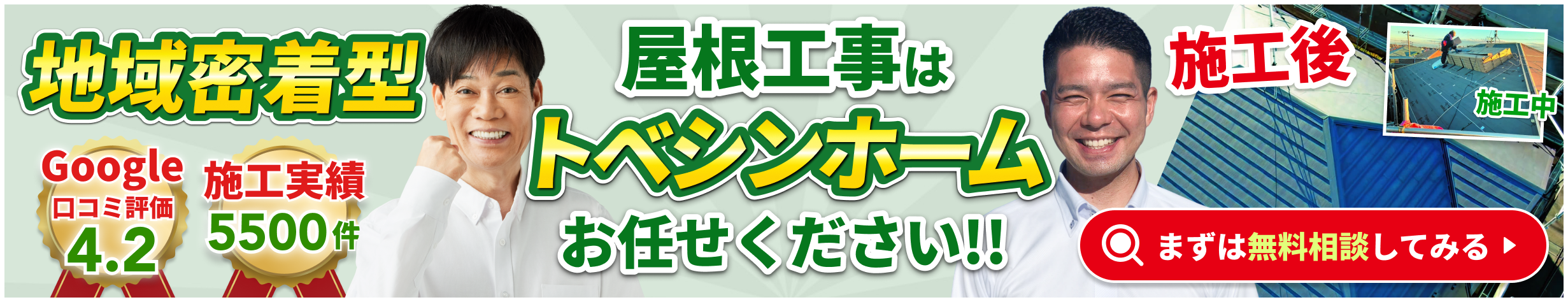
まとめ
屋根カバー工法は、既存の屋根材を撤去せずに新しい屋根材を重ねる工法で、工期短縮やコスト削減というメリットがある一方、重量増加による影響が懸念されることもあります。
一般的な住宅では、スレート屋根にガルバリウム鋼板を施工した場合、約600kg(小型車1台分)の重量増加となりますが、これは住宅全体から見れば限定的な影響しかないことがわかります。
耐震性への影響も、新耐震基準で建てられた住宅であれば問題になることはほとんどありません。
しかし、築年数が古く構造体が劣化している場合や、下地の野地板が傷んでいる場合、既存の屋根が雨漏りしている場合、建物の耐荷重に問題がある場合には、屋根カバー工法は避けるべきでしょう。
屋根カバー工法を検討する際は、建物の状態を専門家に適切に診断してもらい、安全性と経済性のバランスを考慮した判断をすることが重要です。
適切な条件と施工技術があれば、屋根カバー工法は長期間安心して使える優れた屋根リフォーム方法となるでしょう。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。