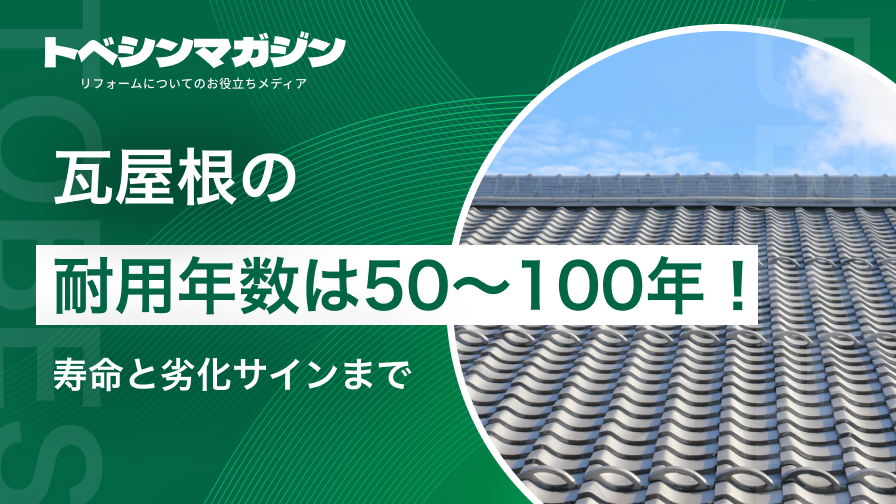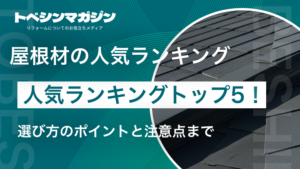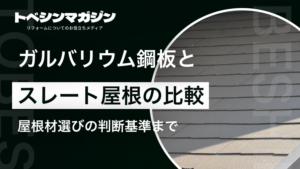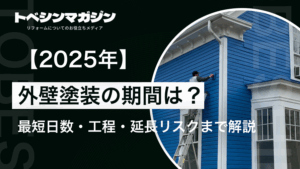「瓦屋根はいつまで持つのだろう?」
「メンテナンスの時期が分からなくて不安…」
「業者に葺き替えを勧められたけど、本当に必要なのかな」
瓦屋根を所有する多くの方が、このような疑問を抱えているのではないでしょうか。
瓦屋根は耐久性に優れた屋根材ですが、築年数が経過すると経年劣化は避けられません。しかし、適切な知識があれば、不必要な工事を避け、最適なタイミングでメンテナンスを行うことが可能です。
特に注意したいのは、瓦自体の寿命と下地材の寿命が異なる点です。見た目は問題なくても、防水シートが劣化していれば雨漏りのリスクが高まります。
この記事では、瓦屋根の種類別の耐用年数から劣化サイン、適切なメンテナンス方法まで詳しく解説します。
この知識を身につければ、あなたの屋根に最適な対処法を見極め、長く安全に使い続けることができるでしょう。
なお、すべての屋根の耐用年数については、こちらの記事で詳しく解説しています。
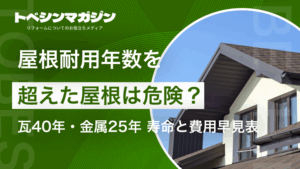
この記事のポイント
- 瓦屋根の耐用年数は50~100年
- 防水シートは20~30年で劣化する
- 適切なメンテナンスで寿命が延びる

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。
専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
瓦屋根の基本的な耐用年数
瓦屋根は日本の伝統的な屋根材であり、その耐久性の高さが大きな特徴です。
瓦屋根の基本的な耐用年数について、以下の3つの視点から解説します。
耐用年数を正しく理解することで、無駄な修繕工事を避け、適切なタイミングで必要なメンテナンスを行うことが可能となります。
耐用年数の目安は50~100年
瓦屋根の耐用年数は、一般的に50~100年と言われています。これは他の屋根材と比較しても非常に長寿命であり、瓦屋根の大きな魅力となっています。
特に日本瓦(粘土瓦)は、1000℃以上の高温で焼成されているため非常に強度が高く、適切なメンテナンスを行えば100年近く使用できる事例も珍しくありません。
ただし、この耐用年数はあくまで瓦自体の寿命であり、定期的なメンテナンスが前提となる点に注意が必要です。
特に漆喰部分や棟瓦の固定部分は15~20年程度で劣化することが多いため、部分的な補修を適切に行うことが瓦屋根を長持ちさせるポイントとなるでしょう。
屋根の耐用年数に不安がある方は、トベシンホームの無料診断をご活用ください。

他の屋根材との耐用年数比較
瓦屋根は他の一般的な屋根材と比較しても、圧倒的に長い耐用年数を誇ります。主な屋根材の耐用年数を比較すると、以下のような違いがあります。
| 屋根材 | 耐用年数 |
|---|---|
| 瓦屋根(粘土瓦) | 50~100年 |
| ガルバリウム鋼板 | 30~50年 |
| スレート屋根 | 20~30年 |
| アスファルトシングル | 20~30年 |
| トタン屋根 | 10~20年 |
このように、瓦屋根は他の屋根材と比較して2~3倍以上の耐用年数があります。初期投資は高くなりますが、長期的に見れば非常にコストパフォーマンスの高い屋根材だと言えるでしょう。
防水シートの耐用年数も把握しておこう
瓦屋根の耐用年数を考える上で忘れてはならないのが、瓦の下に敷かれている防水シート(ルーフィング)の存在です。
防水シートの耐用年数は約20~30年とされており、瓦自体よりも大幅に短いのが現実です。
防水シートが劣化すると、瓦自体に問題がなくても雨漏りの原因となります。特に近年の豪雨や台風の増加により、防水性能の重要性は高まっています。
築20年を超える瓦屋根の住宅では、防水シートの状態を専門家に確認してもらうことをおすすめします。
瓦を一度撤去して防水シートを張り替える『葺き直し工事』を検討することで、瓦屋根の寿命をさらに延ばすことが可能となるでしょう。
瓦の種類別の耐用年数
瓦屋根にはさまざまな種類があり、使用される素材や製造方法によって耐用年数が大きく異なります。
ご自宅の瓦がどのタイプなのかを知ることで、適切なメンテナンス計画を立てることができるでしょう。それぞれの瓦の耐用年数について詳しく解説します。
各種瓦の特性を理解し、自宅の屋根に合った対応を検討しましょう。
和瓦(粘土瓦)の耐用年数
和瓦は日本の伝統的な屋根材で、粘土を高温で焼き上げて製造されています。高い耐久性を持ち、その耐用年数は50~100年と言われています。
特徴的な曲線美を持つ和瓦は、日本建築の美しさを引き立てるだけでなく、雨水を効率よく排水する機能も持ち合わせています。また、粘土を高温で焼成しているため、紫外線や風雨による劣化に強い特性を持っています。
ただし、和瓦は重量があるため、地震の多い日本では耐震性の観点から課題となることもあります。
また、漆喰部分は20~30年程度で劣化するため、定期的なメンテナンスが必要です。適切なメンテナンスを行えば、長期間美しい屋根を保つことが可能です。
釉薬瓦(陶器瓦)の耐用年数
釉薬瓦は、粘土瓦の表面に釉薬(ガラス質の層)をコーティングして焼成した瓦です。表面がガラス質になっているため水が浸透せず、その耐用年数は半永久的と言われています。
釉薬による表面保護があるため、通常の粘土瓦よりも防水性や耐候性に優れています。特に三州瓦や石州瓦などの高品質な釉薬瓦は、100年以上使用された事例も報告されています。
釉薬瓦は塗装によるメンテナンスが不要なため、長期的に見ると維持費が抑えられるメリットがあります。
ただし、漆喰部分や下地の防水シートは経年劣化するため、これらの部分は定期的な点検と補修が必要となるでしょう。
洋瓦の耐用年数
洋瓦は、欧米スタイルの住宅によく使われる屋根材で、粘土を平らに成形して焼成した瓦です。その耐用年数は40~50年程度と言われています。
なだらかな曲線を描く洋瓦は、モダンでスタイリッシュな外観を実現します。粘土を材料としているため、紫外線による劣化が少なく、塗装などのメンテナンスが基本的に不要な点も魅力です。
しかし、和瓦と同様に重量があるため、建物への負荷が大きくなります。また、強風や地震によって瓦がずれることがあるため、定期的な点検が必要です。特に台風の多い地域では、固定方法に注意を払う必要があるでしょう。
無釉薬瓦(いぶし瓦・素焼き瓦)の耐用年数
無釉薬瓦は、釉薬を施さずに焼成した瓦で、いぶし瓦や素焼き瓦などが含まれます。その耐用年数は30~60年程度です。
いぶし瓦は、焼成時に還元炎でいぶすことで表面に炭素被膜を形成させています。この炭素被膜が瓦を保護し、耐久性を高めています。寺院や神社などの伝統的な建築物に多く使用されてきました。
しかし、経年劣化により表面の炭素被膜が徐々に剥がれると、耐水性が低下していきます。
素焼き瓦も同様に、表面保護がないため時間の経過とともに吸水性が高まり、凍結による割れのリスクが増加するでしょう。定期的な点検と必要に応じた部分的な交換が重要となります。
セメント瓦・モニエル瓦の耐用年数
セメント瓦は、セメントを主成分として製造された瓦です。モニエル瓦はセメントに砂利を混ぜたコンクリート瓦の一種で、これらの耐用年数は20~40年程度です。
セメント瓦は和瓦や陶器瓦と比較して安価に製造できるため、経済性に優れています。また、粘土瓦より軽量なため、建物への負担が少ない利点もあります。
ただし、表面の塗装が紫外線や雨風などの影響で劣化するため、10~20年ごとに塗装メンテナンスが必要となります。
塗装が劣化すると、瓦本体の劣化が加速し、ひび割れやコケの発生などの問題が生じやすくなるでしょう。定期的な塗装メンテナンスを行うことで、耐用年数を延ばすことが可能です。
瓦屋根の耐用年数を左右する要素
瓦屋根の耐用年数は一概に決まるものではなく、様々な要素によって大きく左右されます。
ここでは、瓦屋根の耐用年数に影響を与える主な要素について解説します。
これらの要素を理解することで、自宅の瓦屋根がどれくらい持つのか、より正確に予測することができるでしょう。
要素1:施工品質の影響
瓦屋根の耐用年数を大きく左右する要素として、施工品質の影響は見逃せません。優れた施工技術で取り付けられた瓦屋根は、その耐用年数を最大限に発揮できるでしょう。
特に重要なのは瓦の固定方法です。従来の土葺き工法と比較して、現在主流となっているガイドライン工法では、瓦を一枚一枚釘やビスで固定するため、台風や地震に強い構造となっています。
また、防水シートの施工状態も耐用年数に大きく影響します。シートにしわや破れがあると、瓦の下から水が侵入する原因となります。
棟部分の施工も重要で、漆喰の塗り方や棟瓦の固定方法が不適切だと、早期に劣化が進むことがあるでしょう。
要素2:地域・気象条件の影響
瓦屋根の耐用年数は、建物が立地する地域や気象条件によっても大きく変わります。特に影響が大きいのは、降雨量、強風、気温変化、そして日照量です。
台風の多い沿岸部では強風による瓦のずれや飛散リスクが高まり、耐用年数が短くなる傾向があります。
また、寒冷地では水分の凍結と融解の繰り返しによる「凍害」が発生し、瓦にひび割れを引き起こすことがあるでしょう。
海に近い地域では塩害の影響も無視できません。塩分を含んだ潮風が瓦や金具を侵食し、劣化を早める原因となります。
さらに、日照量の多い地域では紫外線による漆喰の劣化が加速する傾向にあるのです。
要素3:屋根勾配と構造の影響
瓦屋根の耐用年数には、屋根の勾配(傾斜)と構造も大きく影響します。適切な勾配がない屋根では、雨水や雪の排水効率が低下し、瓦の間に水が溜まりやすくなるでしょう。
一般的に、瓦屋根に適した勾配は4寸から5寸(約22度から27度)とされています。これより緩い勾配の場合、雨漏りのリスクが高まり、防水シートへの負担も増加するため、耐用年数が短くなる傾向があります。
また、屋根の複雑さも耐用年数に影響します。谷や棟が多い複雑な形状の屋根では、水がたまりやすい箇所が増え、そこから劣化が進行しやすくなります。
さらに、下地となる野地板の品質や厚みも、瓦屋根全体の耐久性に大きく関わってくるのです。
瓦屋根の劣化サイン
瓦屋根の劣化は、いくつかの特徴的なサインとして現れます。これらのサインを早期に発見することで、適切なタイミングでメンテナンスを行い、屋根の寿命を延ばすことができるでしょう。
代表的な劣化サインについて解説します。
これらのサインが見られた場合は、早めに専門業者による点検を検討することをおすすめします。
サイン1:瓦のひび割れと欠け
瓦のひび割れや欠けは、瓦屋根の劣化において最も目視しやすいサインです。これらの損傷は、強風や落下物による物理的な衝撃、あるいは凍結融解の繰り返しによって引き起こされることが多いでしょう。
特に気をつけたいのは、複数の瓦にひび割れが見られる場合です。これは材質の経年劣化が進んでいる可能性が高く、今後さらに多くの瓦が破損するリスクがあります。
また、欠けた瓦の破片が屋根の上や庭に落ちているのを発見した場合も、早急な対応が必要です。
ひび割れや欠けを放置すると、そこから雨水が侵入し、防水シートや野地板の劣化を引き起こします。部分的な交換で対応できる場合が多いですが、劣化が広範囲に及ぶ場合は大規模な修繕が必要となるでしょう。
サイン2:瓦のズレと浮き
瓦のズレや浮きは、地震や強風などの外部からの力によって発生することが多い劣化サインです。瓦と瓦の間に隙間が生じると、そこから雨水が侵入するリスクが高まります。
特に注意が必要なのは、軒先や棟部分の瓦のズレです。これらの箇所は風の影響を受けやすく、一度ズレが生じると連鎖的に他の瓦もズレていく可能性があります。
また、瓦の浮きは固定釘の劣化や抜けが原因となっていることが多いでしょう。
近年では2020年に義務化された「ガイドライン工法」によって、瓦を一枚一枚釘やビスで固定することが標準となっています。古い工法で施工された屋根は、ズレや浮きが生じやすいため、定期的な点検が特に重要となるのです。
サイン3:漆喰の剥がれと劣化
漆喰の剥がれや劣化は、瓦屋根の耐久性に直接影響を与える重要な劣化サインです。漆喰は棟瓦を固定するために使用される材料で、一般的に15~20年程度で劣化が進みます。
劣化初期には漆喰表面のひび割れが目立ち始め、徐々に剥がれや欠落が進行します。特に雨樋近くの漆喰剥がれは要注意で、そこから雨水が侵入し屋根内部に浸水する原因となる可能性が高いでしょう。
漆喰の劣化を放置すると、棟瓦の固定力が弱まり、強風で棟全体が崩れるリスクも高まります。
築10年以上経過した住宅では、漆喰の状態を定期的に確認し、必要に応じて補修を行うことが重要です。
サイン4:棟瓦の歪みと崩れ
棟瓦の歪みや崩れは、屋根の重要な劣化サインの一つです。棟は屋根の最も高い部分で、風雨の影響を直接受けるため、他の部分より劣化が早く進むことがあります。
棟瓦の歪みは、下部の漆喰の劣化や土台の沈下が原因となることが多いでしょう。歪みが進行すると、瓦同士の隙間が広がり、雨水の侵入経路となります。
さらに深刻な場合は、棟瓦が落下するリスクもあり、安全面での懸念も生じます。
棟瓦の問題は、建物全体の雨漏りに直結する重要な症状です。早期発見・早期対応が特に重要であり、歪みを発見した時点で専門業者による「棟積み直し工事」を検討すべきでしょう。
適切な処置を行えば、屋根全体の寿命を延ばすことが可能となります。
サイン5:雨漏り
雨漏りは瓦屋根の劣化における最も深刻なサインであり、すでに屋根の機能が著しく低下している証拠です。
天井のシミや壁のカビ、雨の日に感じる湿った臭いなどが雨漏りの兆候として現れます。
雨漏りの原因として多いのは、瓦のズレやひび割れ、漆喰の剥がれなどですが、見た目では問題がなくても防水シートの劣化による場合もあるでしょう。
特に築20年以上経過した住宅では、防水シートの耐用年数を超えている可能性が高いのです。
雨漏りを発見したら、応急処置として雨漏り箇所の下にバケツを置くなどの対応をしつつ、早急に専門業者へ連絡することが重要です。
放置すると建物の木部が腐食し、構造体にも悪影響を及ぼす可能性があります。
上記の症状がどれか1つでも確認できた際には、早急な補修工事が必要な可能性があります。
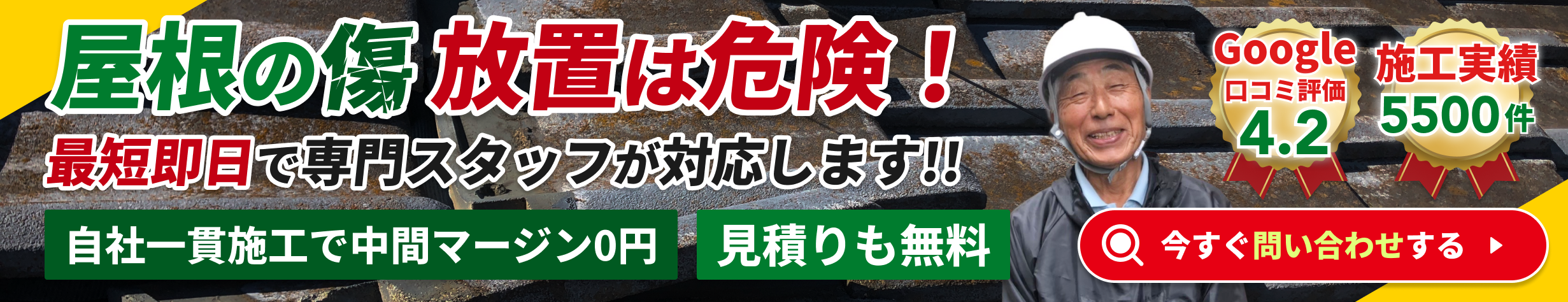
瓦屋根の適切なメンテナンス時期
瓦屋根を長持ちさせるためには、適切なタイミングでのメンテナンスが欠かせません。いつ、どのようなメンテナンスを行うべきかを知ることで、無駄な出費を抑えつつ屋根の寿命を最大限に延ばすことができるでしょう。
一般的に、瓦屋根のメンテナンスは築10年を目安に最初の点検を行うことをおすすめします。この時期には漆喰のひび割れや瓦のわずかなズレが現れ始めることが多く、早期発見・早期対応が可能となります。
築15〜20年経過すると、防水シートの劣化が始まる時期となります。この頃には漆喰の補修や部分的な瓦の交換など、中規模の修繕が必要となるケースが増えてくるでしょう。特に棟瓦の固定部分は注意が必要です。
築30年以上が経過すると、防水シートが耐用年数を超えているため、葺き直しや葺き替えなどの大規模修繕を検討すべき時期となります。
定期的な点検と適切なメンテナンスを行うことで、瓦屋根本来の長寿命を実現できるのです。
瓦屋根の寿命を延ばすメンテナンス方法
瓦屋根は耐久性に優れていますが、適切なメンテナンスを行うことでさらに寿命を延ばすことが可能です。状態や劣化度合いによって最適なメンテナンス方法は異なります。
ここでは主な3つのメンテナンス方法について解説します。
適切な方法を選択することで、費用を抑えながら屋根の機能を回復させることができるでしょう。
方法1:部分的な補修
部分的な補修は、瓦屋根の局所的な劣化に対応するメンテナンス方法です。具体的には、割れた瓦の交換、漆喰の補修、棟瓦の積み直しなどが含まれます。
一般的な瓦の交換費用は1枚当たり1~5万円程度で、漆喰の補修は5~10万円程度が相場です。棟瓦の積み直しになると20~40万円程度かかるケースが多いでしょう。
部分的な補修は比較的低コストで済み、早期に対応することで大規模な工事を防ぐことができます。
特に築10~15年程度の住宅では、この部分補修を適切に行うことで、屋根全体の寿命を大幅に延ばすことが可能です。
方法2:防水シートの張り替え
防水シートの張り替えは、瓦自体の状態は良好でも防水シートが劣化している場合に適したメンテナンス方法です。
「葺き直し工事」とも呼ばれ、既存の瓦を一時的に取り外し、下地の防水シートを新しいものに交換します。
葺き直し工事の費用は一般的な戸建て住宅で70~150万円程度です。工期は1~2週間程度で、瓦を再利用するため新しい瓦の材料費が不要となり、葺き替え工事と比較してコストを抑えられるメリットがあります。
築20年前後の住宅では、防水シートの劣化が進んでいることが多いため、この工事を検討すべきでしょう。特に瓦自体に大きな損傷がなく、下地の状態を確認・改善したい場合に適しています。
方法3:葺き替え工事
葺き替え工事は、既存の瓦屋根を全て撤去し、下地から新しく施工し直す最も大規模なメンテナンス方法です。瓦自体の劣化が進んでいる場合や、建物全体の耐震性を高めたい場合に選択されます。
一般的な戸建て住宅(30坪程度)の葺き替え工事費用は150~200万円程度で、工期は2~3週間かかるのが一般的です。
下地の野地板や防水シートも含めて全て新しくなるため、新築時と同様の性能を取り戻すことができるでしょう。
特に築30年以上が経過した住宅や、部分的な修理では対応できないほど劣化が広範囲に及んでいる場合は葺き替えを検討すべきです。
近年では、伝統的な瓦から軽量化された瓦や、別の屋根材への変更も選択肢となっています。
瓦屋根のメンテナンス・工事はトベシンホームにご相談ください

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
| 本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
| 電話番号 | 0120-685-126 |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
トベシンホームは、瓦屋根の修繕・葺き替え工事において豊富な実績を持つ外装リフォーム専門店です。千葉県・埼玉県・茨城県を中心に、瓦の種類や劣化状態に応じた最適なメンテナンス方法をご提案しています。
当社の強みは、瓦屋根の特性を熟知した専門スタッフによる的確な診断力にあります。和瓦から洋瓦、セメント瓦まで、各種瓦屋根の特徴を理解した上で、建物の状態や予算に合わせた工事プランを作成します。
調査から施工、アフターフォローまでを自社スタッフが一貫して担当するため、高品質な工事と適正価格を両立できるのが特徴です。また、補助金制度や火災保険の活用についても経験豊富なスタッフがサポートしています。
瓦屋根の耐用年数や劣化状態でお悩みの方は、まずは当社の無料点検サービスをご利用いただき、専門家の視点から現状を確認してみましょう。

まとめ
瓦屋根の耐用年数は50~100年と非常に長く、他の屋根材と比較しても優れた耐久性を持っています。しかし、瓦の種類によって耐用年数は大きく異なり、和瓦や釉薬瓦は50~100年である一方、セメント瓦は20~40年程度と短くなる点に注意が必要です。
瓦自体の耐用年数だけでなく、防水シートの寿命(20~30年)も考慮すべき重要なポイントです。瓦が健全でも防水シートが劣化していれば雨漏りのリスクが高まります。
耐用年数を左右する要素としては、施工品質、地域・気象条件、屋根勾配などが挙げられます。瓦のひび割れ、ズレ、漆喰の剥がれなどの劣化サインを早期に発見し、適切なメンテナンスを行うことが大切です。
築10年での点検、15~20年での中規模修繕、30年以降での大規模修繕と、計画的なメンテナンスを行うことで、瓦屋根本来の長寿命を実現できるでしょう。
状況に応じて部分補修、防水シートの張り替え、葺き替え工事などの適切な方法を選択することが重要です。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。