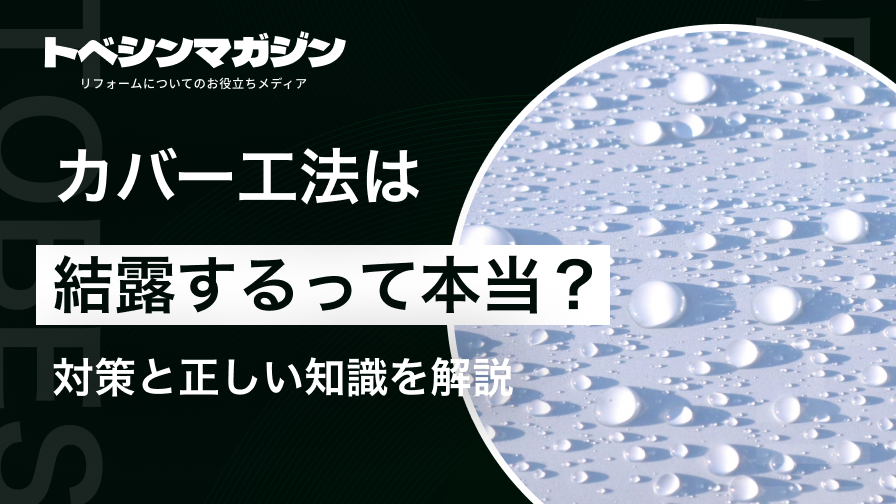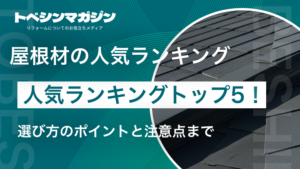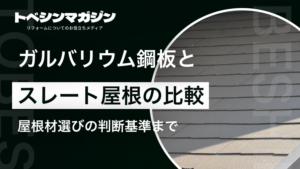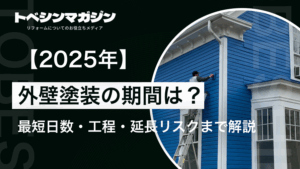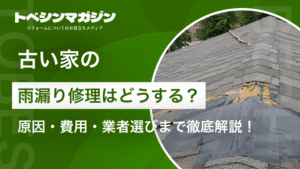「屋根カバー工法って結露するって本当?」
「カバー工法で結露したらカビが発生するんじゃないの?」
「どんな対策をすれば結露を防げるんだろう」
屋根リフォームを検討する際、こうした不安を抱えている方は少なくないでしょう。特に、カバー工法は既存の屋根材を撤去せずに新しい屋根材を重ねる工法なので、その間に結露が発生するのではないかと心配される方も多いはずです。
結論として、適切に施工された屋根カバー工法では基本的に結露の心配はありません。
しかし、特定の屋根材や劣化状態によっては注意が必要な場合もあるのです。
この記事では、屋根カバー工法における結露のメカニズムから、結露やカビを防ぐ効果的な対策、そして適切な屋根材選びのポイントまで詳しく解説します。
正しい知識を身につけることで、安心して屋根カバー工法によるリフォームを進めることができるでしょう。
また屋根カバー工法の全容については、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

この記事のポイント
- 正しい施工なら結露の心配は少ない
- 一部の屋根材には注意が必要
- 換気棟と防水シートで結露を防止できる

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。
専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
屋根カバー工法は基本的に結露の心配はない
屋根カバー工法では、結露の心配はほとんどないと言えるでしょう。なぜなら、適切な施工が行われていれば、湿気の排出経路が確保されるためです。
ここでは、カバー工法の基本的な仕組みから結露問題の誤解、発生メカニズムまで詳しく解説します。
屋根のリフォームにおいて、カバー工法は費用対効果に優れた選択肢の一つです。
屋根カバー工法の基本的な仕組み

屋根カバー工法とは、既存の屋根材を撤去せず、その上に新しい屋根材を重ねる工法です。まず既存屋根の状態を確認し、必要な補修を行います。
次に重要なのが防水シートの敷設です。この防水シートが結露対策の核となるのです。万が一結露が発生しても、シートが水の浸透を防ぎ、外部へ排出する役割を果たします。
防水シートの上には新しい屋根材を設置し、屋根の頂点には換気棟を取り付けます。この換気棟によって小屋裏の空気が循環され、湿気がこもりにくい環境が整うのです。
このシステムにより、カバー工法では基本的に結露の心配なく、コストを抑えた屋根リフォームが可能となっています。
結露問題に関する誤解と真実
「カバー工法は結露するのではないか」という不安を持つ方は多いですが、これは大きな誤解です。適切に施工された場合、結露のリスクは極めて低いと言えるでしょう。
その理由は防水シートにあります。古い屋根と新しい屋根の間に敷かれるこのシートは、万が一結露が起きても水分が下に浸透しないよう防ぐ役目を果たすのです。
また「二重屋根だから湿気がこもる」という誤解もあります。しかし、換気棟を適切に設置することで小屋裏の空気を循環させ、湿気を効率的に排出できます。
最近では透湿性の高い防水材も普及し、内部の湿気を外に逃がしつつ、外からの水は防ぐという機能も向上しています。技術の進歩により、結露のリスクはさらに低減されているのです。
結露が発生するメカニズム
結露は空気中の水蒸気が冷たい面に触れると発生します。屋根の場合、室内の暖かい空気が上昇し、外気温が低い屋根材と接触することで起こる現象です。
特に冬場は室内外の温度差が大きくなるため、結露が発生しやすい環境となります。カバー工法で懸念されるのは、既存屋根と新屋根の間のスペースでの結露です。
ただし、防水シートの設置と換気棟による空気循環が適切に行われていれば、この懸念はほぼ解消されます。結露は放置するとカビや腐食の原因となるため、湿気を排出する仕組みづくりが重要です。
適切な施工業者を選ぶことで、結露の心配なく安心して屋根カバー工法を選択できるでしょう。
【注意】一部の屋根材では結露リスクがある
基本的に屋根カバー工法では結露の心配は少ないものの、一部の屋根材では結露リスクが高まる場合があります。屋根材の種類や劣化状態によって、注意が必要なケースを解説します。
適切な判断で安全な屋根カバー工法を選択しましょう。
結露の可能性がある屋根材
すべての屋根材がカバー工法に適しているわけではありません。特に吸水率の高い屋根材では、結露のリスクが高まります。
代表的な例は「パミール」と呼ばれる屋根材で、吸水率が約20%と非常に高いのが特徴です。一般的なアスファルトシングル(吸水率1%以下)の20倍以上の水分を含む可能性があります。
また「カラーベスト」や「コロニアル」などのスレート系屋根材も吸水率が約8%程度あり、注意が必要です。これらの屋根材の上にカバー工法を施すと、含まれた水分が蒸発できずに内部に閉じ込められ、結露の原因となることがあります。
こうした高吸水率の屋根材では、カバー工法よりも葺き替えを検討した方が安全でしょう。
劣化状態によっては結露リスクも
屋根材の種類だけでなく、劣化状態によっても結露リスクは変化します。長年の風雨にさらされた屋根材は、目に見えない水分を多く含んでいることがあります。
特に注意すべきは、野地板が水分を含んでいる場合です。野地板とは屋根材を支える下地のことで、ここに水分が染み込んでいると、カバー工法後に内部で蒸発できずに結露の原因となります。
また、屋根材の表面にひび割れや欠損がある場合も危険信号です。こうした状態では既に内部に水分が侵入している可能性が高いです。
現状で雨漏りしている場合や屋根全体の劣化が激しい場合は、古い屋根材を撤去して新しく葺き替える「葺き替え工法」を選択するべきでしょう。
屋根カバー工法の結露はカビ発生の原因になる
屋根カバー工法で結露が発生した場合、最も懸念すべき問題の一つがカビの発生です。結露によって生じた水分は、暗く湿った環境を好むカビの絶好の繁殖場所となります。
カビが発生すると、屋根材や野地板などの木材部分の腐食を促進させ、建物の構造に深刻なダメージを与える可能性があります。特に木材が腐食すると、屋根の強度が低下し、最悪の場合は屋根の一部が崩落するリスクも考えられるでしょう。
また、カビの胞子は空気中に舞い、室内に入り込むことで、アレルギー症状や呼吸器系の疾患を悪化させる原因となります。さらに、建物の断熱性能も低下し、光熱費の上昇にもつながる問題です。
こうした問題を防ぐためには、適切な結露対策を施したカバー工法を選ぶことが重要となります。
屋根カバー工法で結露とカビを防止する方法
屋根カバー工法で結露やカビの発生を防ぐには、適切な対策が不可欠です。ここでは効果的な3つの防止方法を紹介します。
これらの対策を適切に実施することで、結露のリスクを大幅に低減し、長期間安心して使える屋根を実現できるでしょう。
信頼できる業者に依頼し、これらの対策を確実に実施することが重要です。
方法1:高性能な防水シートを使用する
カバー工法における結露防止の第一歩は、高性能な防水シートの選択です。単なる防水性だけでなく、透湿性も兼ね備えたシートを使用することが重要です。
防水シートは既存の屋根と新しい屋根の間に敷設され、万が一結露が発生した場合でも、水分が下地に浸透するのを防ぎます。特に粘着層付改質アスファルトルーフィングのような高品質な防水シートは、水の侵入を確実に防ぐ効果があります。
しかし、防水性が高すぎると今度は内部の湿気が逃げられなくなるという問題が生じます。そこで近年は透湿性を併せ持つシートが推奨されています。
これにより内部の湿気を外に逃がしつつ、外部からの水は防ぐという理想的な環境を作り出せるのです。
業者に依頼する際は、使用する防水シートの性能について必ず確認しましょう。
方法2:換気棟を適切に設置する
カバー工法で結露を防ぐ重要な対策の一つが、換気棟の設置です。換気棟とは屋根の頂点に取り付ける換気機能を持った部材で、屋根内部や小屋裏の湿気を効率的に排出する役割を果たします。
換気棟は小屋裏の空気を循環させ、湿気のこもりを防ぎます。暖かい空気は上昇する性質があるため、屋根の最も高い位置に設けることで自然な空気の流れを作り出します。この自然換気により、結露の発生を抑制できるのです。
設置場所は屋根の頂点(棟)が基本ですが、屋根の形状によっては複数設置する場合もあります。効果的な換気を実現するには、軒先などの下部からも空気が入る経路を確保することが大切です。
適切に換気棟を設置することで、結露リスクを大幅に低減できるでしょう。
方法3:透湿ルーフィングを活用する
結露対策として効果的なのが、透湿ルーフィングの活用です。これは湿気を通すが水は通さないという特殊な機能を持った下地材です。
通常の防水シートと異なり、透湿ルーフィングは屋根内部の湿気を外部に逃がす透湿性に優れています。これにより屋根内部に湿気がこもりにくくなり、結露の発生を抑制できるのです。
透湿ルーフィングは既存の屋根の上に敷く前に、必要に応じて下地の補修を行うことが重要です。特に野地板に湿気が含まれている場合は、乾燥させてから施工するようにしましょう。
現在は様々なメーカーから高性能な透湿ルーフィングが販売されています。耐久性や透湿性能を考慮し、信頼できる製品を選ぶことをお勧めします。
屋根カバー工法では適切な屋根材を選ぶことが重要
屋根カバー工法を成功させるためには、使用する屋根材の選定が非常に重要です。適切な屋根材を選ぶことで、結露やカビの発生リスクを低減し、耐久性の高い屋根を実現できます。
一般的に結露リスクの低い金属系の屋根材がカバー工法に適しています。特にガルバリウム鋼板は軽量で耐久性に優れ、カバー工法の屋根材として人気があります。
耐用年数は20〜30年程度で、コストも比較的抑えられる点が魅力です。
ジンカリウム鋼板も良い選択肢の一つで、表面に石粒がコーティングされているため断熱性に優れています。耐用年数が30〜50年と長く、塗装の必要がないため維持費を抑えられる利点があります。
アスファルトシングルは軽量で施工性に優れ、吸水率が1%以下と低いため結露リスクを抑えられます。北米やカナダで広く使用されており、耐震性にも優れているのが特徴です。
屋根材の選定には、建物の構造や気候条件、予算なども考慮する必要があります。信頼できる業者に相談し、最適な屋根材を選びましょう。
屋根カバー工法で使用する屋根材のおすすめ情報や選び方について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。
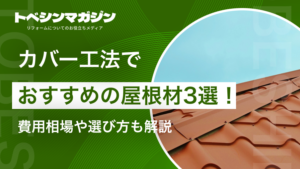
屋根カバー工法ならトベシンホームへ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
| 本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
| 電話番号 | 0120-685-126 |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
トベシンホームは関東圏で多数の屋根カバー工法の施工実績を持つ、信頼の外装リフォーム専門店です。屋根カバー工法における結露対策に特化した施工技術と豊富な知識を有しています。
当社では屋根の状態を詳細に診断し、結露リスクを最小限に抑える最適な工法と屋根材をご提案します。
特に高性能防水シートの選定と換気システムの設計に力を入れており、結露やカビの心配がない安心の屋根リフォームを実現しています。
施工は経験豊富な自社職人が担当し、調査から施工、アフターフォローまで一貫した体制で対応します。これにより高品質な施工と適正価格を両立しています。
屋根カバー工法の結露対策についてお悩みの際は、まずは無料診断をご利用ください。最短即日での現地調査で、あなたの屋根に最適な提案をさせていただきます。

まとめ
屋根カバー工法は、基本的に結露の心配が少ない工法です。適切な防水シートの使用と換気システムの設置により、結露のリスクを大幅に低減できることがわかりました。
ただし、パミールなど吸水率の高い屋根材や、劣化が進んで水分を多く含んだ状態の屋根には注意が必要です。こうした場合は、カバー工法ではなく葺き替え工法を選択する方が安全でしょう。
万が一結露が発生すると、カビや建材の腐食などの深刻な問題につながる可能性があります。これを防ぐためには、高性能な防水シートの使用、換気棟の適切な設置、透湿ルーフィングの活用という3つの対策が効果的です。
また、カバー工法に適した屋根材を選ぶことも重要なポイントとなります。ガルバリウム鋼板やジンカリウム鋼板、アスファルトシングルなどは、その特性からカバー工法に適した選択肢といえるでしょう。
適切な知識と信頼できる業者選びにより、結露の心配なく、長期間安心して使える屋根リフォームを実現できます。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。