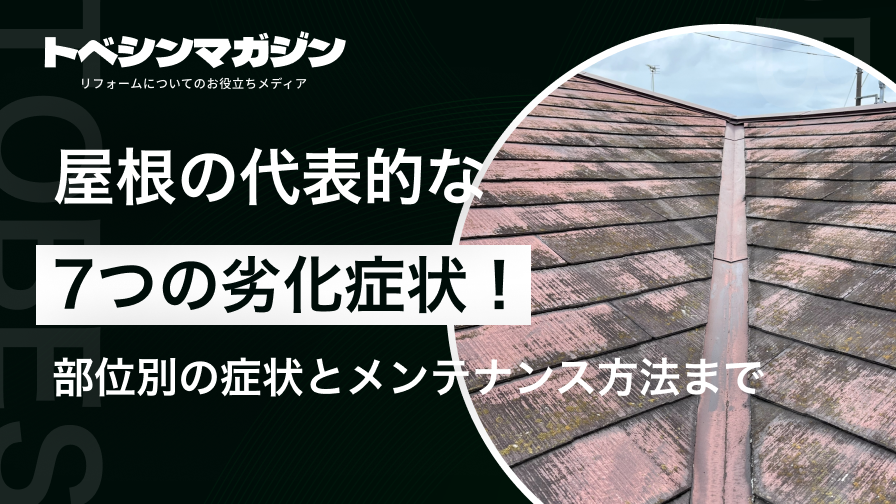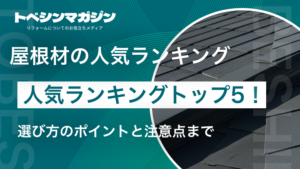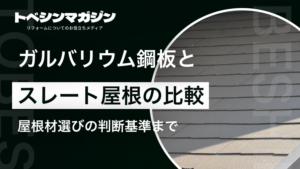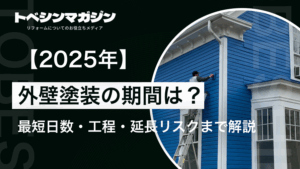「屋根の色が薄くなってきたけど、これって劣化?」
「雨漏りする前に対処したいけど、どんな症状に注意すべき?」
「業者に言われるがまま工事するのは不安…自分でも判断できるようになりたい」
屋根の劣化は見過ごしやすいものですが、放置すると雨漏りなど深刻な問題に発展することがあります。特に築10年以上の住宅では、屋根材の種類を問わず何らかの劣化症状が現れ始めるでしょう。
しかし、いつメンテナンスすべきか、どの症状が危険なのかを判断するのは簡単ではありません。適切な時期に必要な対応ができれば費用を抑えられますが、放置すれば高額な修繕工事が必要になることも。
この記事では、屋根材の代表的な7つの劣化症状から、部位別の異常サイン、効果的なメンテナンス方法まで詳しく解説します。
地上から安全に確認できるポイントも紹介しているので、専門知識がなくても自宅の屋根状態を把握できるようになります。屋根の健康診断のガイドとして、ぜひ参考にしてください。
なお、屋根工事に最適なタイミングについては以下の記事を参考にご検討ください。
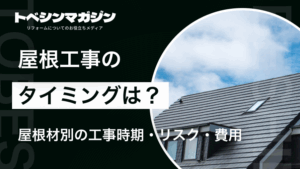
この記事のポイント
- 屋根の劣化は7種類の症状で判断できる
- 地上からも確認できる劣化サインがある
- 状態に応じた適切な工法選びが重要

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。
専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
屋根の劣化症状とは?
屋根の劣化症状とは、経年変化や環境要因によって屋根材や関連部位に現れる異常サインのことです。以下の項目について詳しく解説します。
劣化症状を早期に発見し、適切に対処することで、屋根の寿命を延ばし、高額な修繕費用を抑えることができるでしょう。
屋根が劣化する原因
屋根が劣化する主な原因は、自然環境からの影響と経年変化です。最も大きな影響を与えるのは紫外線と降雨です。
太陽光に含まれる紫外線は屋根材の表面を徐々に劣化させ、色あせや塗膜の剥がれを引き起こします。特に南向きの屋根面は紫外線の影響を強く受けるため、劣化が早く進む傾向があるでしょう。
また、雨水による水分と乾燥の繰り返しは屋根材に大きな負担をかけます。特に雨どいが詰まっていると、水はけが悪くなり屋根材の劣化を加速させる原因となります。
寒冷地では凍結と融解の繰り返しによる「凍害」も劣化の要因です。水分が凍ると体積が増加するため、屋根材にひび割れを引き起こすことがあります。
さらに、海岸地域では潮風に含まれる塩分が金属部分の腐食を早める「塩害」も見られます。工場地帯では大気中の化学物質による劣化も考えられるでしょう。
劣化した屋根を放置するリスク
劣化した屋根を放置することは、様々なリスクを伴います。最も深刻なのは雨漏りの発生です。
屋根に穴やひび割れができると、そこから雨水が侵入し、天井や壁にシミができたり、カビが発生したりします。長期間の雨漏りは建物の構造体である木材を腐らせ、最悪の場合は家全体の倒壊につながる可能性もあるでしょう。
また、屋根の断熱性能が低下すると、夏は室内温度が上がり、冬は暖房効率が落ちるため、光熱費の上昇を招きます。特に屋根裏に断熱材がある場合、水分を含むと断熱性能が大幅に低下します。
さらに、劣化した屋根材は強風で飛散するリスクがあり、周囲の人や物に危害を与える可能性もあります。台風や突風の際には特に注意が必要です。
早期発見・早期対応が可能な小規模な修繕を見送ると、最終的には全面的な葺き替えが必要になり、費用が数倍に膨らむこともあります。適切なタイミングでのメンテナンスが重要です。
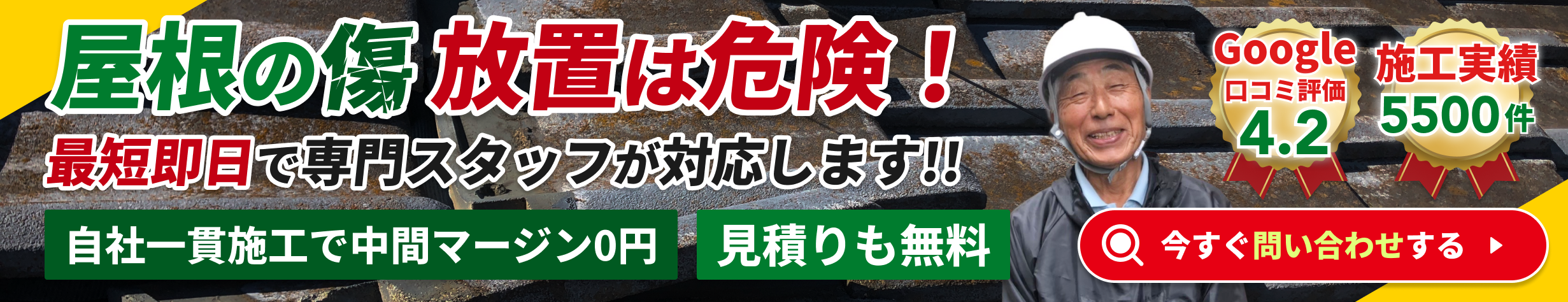
屋根材の代表的な7つの劣化症状
屋根材には共通して現れる劣化症状があります。これらのサインを早期に発見することで、深刻な被害を防ぐことができます。
各症状の緊急度を理解し、適切なタイミングで対応することが大切です。
劣化症状1:色あせと変色

色あせと変色は屋根劣化の初期段階として最も一般的に見られる症状です。新築時に鮮やかだった色が徐々に薄くなり、くすんだ印象になります。
この現象は紫外線や風雨の影響により、屋根材の表面を保護していた塗膜が徐々に劣化していることを示しています。
色あせは見た目の問題だけでなく、屋根材の防水機能が低下し始めている証拠でもあるのです。緊急性は低いものの、今後の劣化進行を示す重要なサインとして注目すべきでしょう。
この段階で適切な塗装メンテナンスを行えば、比較的安価に屋根の寿命を延ばすことが可能です。定期的な点検で色あせに気づいたら、専門業者に相談することをお勧めします。

劣化症状2:コケ・カビの発生

屋根にコケやカビが発生している状態は、単なる見た目の問題ではありません。
特に北向きの屋根面や日陰になる部分には、緑色や黒色のコケが発生しやすい傾向があります。コケは根を張ることで屋根材に微細なひび割れを引き起こし、水分侵入の経路を作ってしまうのです。
湿気の多い環境では、カビの繁殖によって塗膜の劣化がさらに加速する悪循環が生じることもあります。
この症状が見られる場合は、専門業者による洗浄と再塗装を検討すべきでしょう。放置すると雨水の侵入リスクが高まり、屋根下地の腐食につながる恐れがあります。
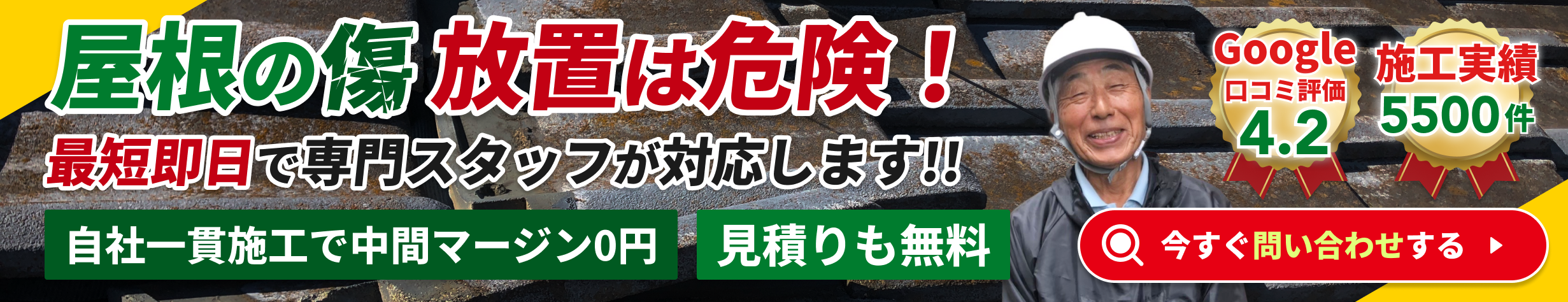
劣化症状3:ひび割れと欠け

屋根材のひび割れや欠けは、劣化が相当進行している証拠であり、早急な対応が必要なサインです。これらの損傷は、強風や落下物による物理的な衝撃、あるいは凍結融解の繰り返しによって引き起こされることが多いでしょう。
重要なポイントは、スレート瓦の端部や角にできるひび割れです。これらの部分は応力が集中しやすく、一度ひびが入ると徐々に拡大していく傾向があります。
この症状が見られる場合は、1度業者に点検しうてもらうことがおすすめです。

劣化症状4:塗膜の剥がれ

屋根材の塗膜剥がれは、防水機能が大きく損なわれている警告サインです。塗膜は屋根材を保護する重要な役割を果たしており、この層が剥がれると直接雨水にさらされる状態になります。
瓦屋根以外のほぼすべての屋根材に見られる症状で、スレート屋根やガルバリウム鋼板屋根では特に注意が必要です。塗膜が剥がれた部分からは雨水が浸入し、下地の劣化を急速に進行させる恐れがあります。
この状態を発見したら早急に専門業者による点検を依頼し、状況に応じた補修や再塗装を検討すべきでしょう。適切な対応が遅れると、部分的な修理では済まなくなる可能性があります。
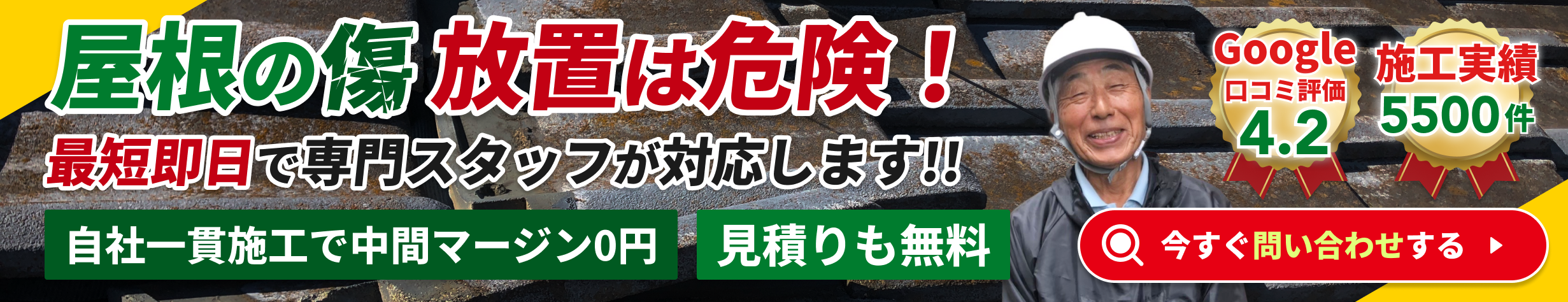
劣化症状5:錆びの発生

錆びの発生は金属屋根特有の劣化症状で、トタンやガルバリウム鋼板などで見られます。
金属屋根では主に「赤錆び」と「白錆び」の2種類が発生します。赤錆びは鉄部分の腐食で、特に傷ついた部分や異種金属との接触部分に現れやすいのです。一方、白錆びは亜鉛めっき層の酸化によるもので、湿気の多い環境でよく見られます。
注意すべきは「もらいサビ」と呼ばれる現象です。屋根上のアンテナや設備機器など他の錆びた金属からの接触で発生し、徐々に広がっていきます。
錆びを発見したら範囲と程度を確認し、専門業者による適切な処置が必要です。早期対応によって部分的な修理で済むことも多く、全面的な葺き替えを避けられる可能性があります。
放置すると錆びが内部に広がり、最終的には穴が開いてしまうでしょう。
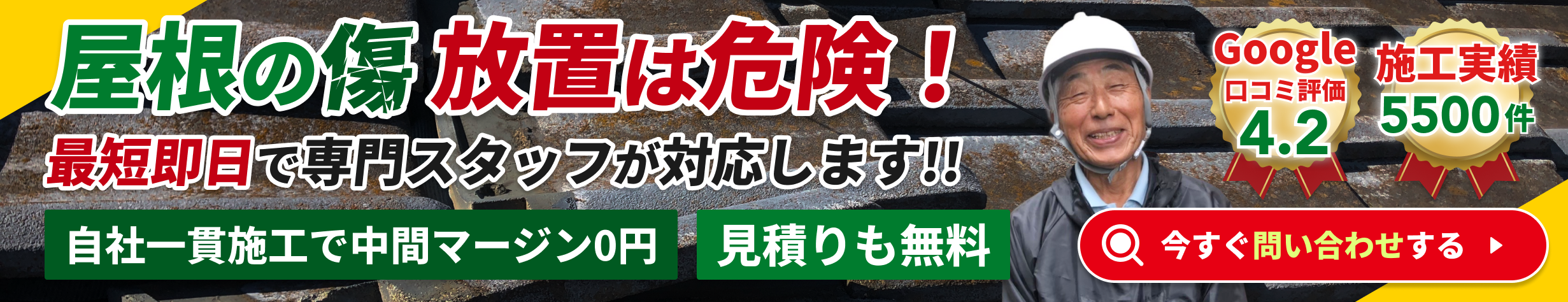
劣化症状6:屋根材の浮きと変形

屋根材の浮きや変形は、固定部分の劣化や下地の状態変化によって引き起こされる深刻な症状です。この状態では強風時に屋根材が飛散するリスクが高まります。
浮きの主な原因は固定釘やビスの緩み、腐食です。特に瓦棒葺きトタン屋根では芯木に釘で留めている構造のため、釘の緩みが屋根材のズレや浮きを引き起こしやすいという特徴があります。
変形については熱による膨張収縮の繰り返しや建物自体の経年変化が影響します。
なお、屋根全体がうねるように反っている場合は、下地の野地板に問題が生じている可能性が高いでしょう。
こうした症状が見られる場合、雨水の侵入経路となり雨漏りのリスクが非常に高まります。部分的な補修で対応できることもありますが、広範囲に及ぶ場合は葺き替えやカバー工法による大規模リフォームを検討すべきです。
早期発見と適切な対応が住まいを守るために不可欠となります。
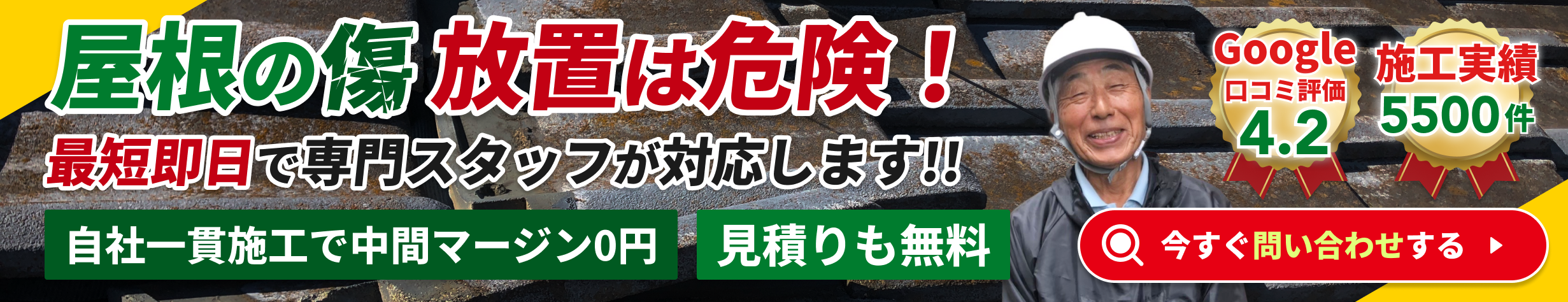
劣化症状7:屋根材の破損と欠落

屋根材の破損や欠落は最も深刻な劣化症状であり、即時対応が必要な状態です。台風や突風、落雪、飛来物などの外的要因、あるいは経年劣化による内的要因で引き起こされます。
漆喰は15〜20年程度で劣化するため、築年数の経った住宅では特に注意が必要です。
破損部分からは直接雨水が侵入するため、雨漏りのリスクは非常に高いでしょう。さらに、一部の屋根材が欠けると周囲の屋根材にも負担がかかり、連鎖的に被害が広がる恐れがあります。
この状態では応急処置としてブルーシートで覆うなどの対策をした上で、早急に専門業者に連絡することが重要です。状況によっては部分修理ではなく、葺き替え工事が必要になることも少なくありません。
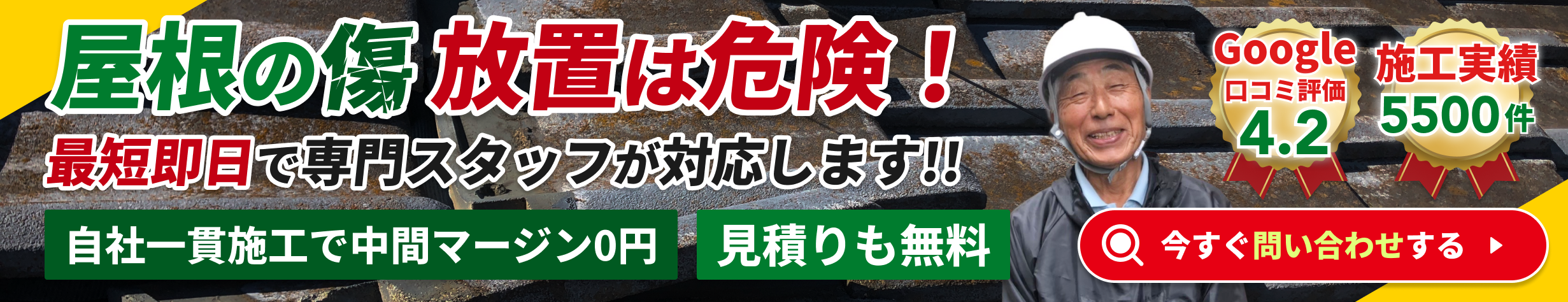
地上から確認できる屋根劣化のサイン
屋根に上らなくても、地上から安全に確認できる劣化サインがあります。定期的に以下のポイントをチェックしましょう。
これらのサインを早期に発見することで、屋根の健康状態を把握できます。
雨樋まわりの異常

雨の日に観察すると、雨どいから水があふれ出ていないか確認できます。継ぎ目からの水漏れも要注意で、これは接合部の劣化を示しています。
雨どい自体の変形や破損も見逃せないポイントです。特に強風や積雪の後は注意が必要でしょう。変形した雨どいは適切に排水できず、外壁を伝って雨水が流れる原因となります。
さらに、雨どい内部に屋根材の破片や砂状の粒子が見られる場合は、屋根材が劣化して崩れている可能性があります。これは重大な劣化のサインと考えるべきでしょう。
軒天の変色やたるみ

軒天(のきてん)は雨漏りの兆候をいち早く表す部位です。変色やシミが見られる場合、屋根から水が侵入している可能性が高いでしょう。
特に黒ずみやカビの発生は注意が必要です。これは湿気が溜まっていることを示し、屋根からの水の侵入や雨どいの詰まりが原因と考えられます。
軒天のたるみや膨らみは、下地の木材が水を吸って膨張している証拠です。触ってみて柔らかく感じる場合は、内部の腐食が進行していることを意味します。
さらに、軒天の一部が剥がれ落ちている場合は、劣化が相当進行している状態です。このような状態では小動物が侵入し巣を作ることもあり、早急な対応が求められます。
外壁の雨染みや変色

外壁の状態からも屋根の劣化を察知できます。特に壁の上部に雨染みや変色が見られる場合、屋根からの水漏れが疑われます。
屋根と外壁の接合部付近に集中して汚れが目立つ場合は、雨水が正常に排水されていない証拠です。これは屋根の水切り板金の劣化や雨どいの不具合が原因かもしれません。
外壁の塗装が剥がれている箇所も要注意です。特に屋根の軒下部分の塗装剥がれは、軒からの水漏れを示していることがあります。
雨の日に外壁を観察すると、異常な水の流れ方が確認できることもあるでしょう。通常とは異なる場所から水が流れ落ちている場合は、屋根の排水経路に問題が生じている可能性があります。
室内から見える劣化兆候

室内からも屋根の劣化サインを発見できます。天井のシミや変色は雨漏りの初期症状として最も一般的です。
雨の日だけ天井が湿っぽく見える場合も注意が必要です。この状態は雨漏りの初期段階であることが多く、放置すると被害が拡大します。
天井だけでなく、壁の上部に現れる変色や膨らみも屋根からの水の侵入を示すサインです。特に窓枠の上部やコーナー部分に注目しましょう。
屋根裏収納がある場合は定期的に確認することで、早期に異常を発見できます。木材の変色や湿り気、カビの発生などが見られたら、屋根からの水の侵入を疑うべきです。
屋根の重要部位別の劣化症状
屋根は様々な部位で構成されており、それぞれ特有の劣化症状があります。部位ごとの特徴を知ることで効果的な点検が可能です。
各部位の役割と劣化傾向を理解することが、適切なメンテナンス計画の第一歩です。
棟部分の劣化症状
棟(むね)は屋根の頂上部分で、最も風雨の影響を受ける部位です。瓦屋根の場合、漆喰の剥がれやひび割れが代表的な劣化症状となります。
漆喰は15〜20年程度で劣化するため、古い住宅では注意が必要です。漆喰が劣化すると棟瓦の固定力が弱まり、台風などの強風で棟全体が崩れる危険性があります。
スレートやガルバリウム鋼板屋根では、棟板金の浮きや錆びが主な劣化症状です。棟板金を固定している釘やビスの緩みにより浮き上がった状態になると、強風で飛散したり変形したりするリスクが高まります。
棟の歪みも重要なチェックポイントです。棟がまっすぐでない場合、地震や強風の影響で屋根全体にダメージが及んでいる可能性があります。
谷部分の劣化症状
谷(たに)は複数の屋根面が交わる部分で、雨水が集中する場所です。この部分は常に水が流れる経路となるため、劣化が特に早く進行します。
谷板金の錆びや腐食は最も一般的な劣化症状です。谷板金は雨水と常に接触するため、防水性能が低下すると雨漏りに直結します。
落ち葉や砂などの堆積も谷部分の大きな問題です。これにより雨水の流れが妨げられ、溢れた水が屋根材の下に浸入するリスクが高まります。
谷部分の防水シートの劣化もチェックポイントです。特に築20年以上の住宅では防水シートの耐用年数を超えている可能性が高く、雨漏りの原因となることがあります。
雨の日に谷から異常な水の流れが見られる場合は、早急な対応が必要となるでしょう。
ケラバ部分の劣化症状
ケラバとは屋根の妻側の端部を指し、強風の影響を最も受けやすい部分です。この部位の劣化は雨水の侵入や屋根材の飛散リスクを高めます。
ケラバ板金(唐草)の浮きや変形は代表的な劣化症状です。強風によって端部から屋根材がめくれ上がるのを防ぐため、しっかりと固定されている必要があります。
木製の破風板が使用されている場合は、腐食や塗装の剥がれもチェックポイントとなります。破風板の腐食はケラバ全体の強度低下につながるためです。
瓦屋根の場合、端部の瓦のズレや浮きが見られることがあります。これは強風で瓦が飛散する危険性を示すサインと言えるでしょう。
スレートやガルバリウム鋼板屋根では、端部の固定が緩んでいないか確認することが重要です。端部からの雨水の侵入は屋根下地の急速な劣化を引き起こします。
軒先部分の劣化症状
軒先は屋根の最も外側にある部分で、雨水を適切に排水する重要な役割を担っています。この部分の劣化は外壁への雨水の侵入を招きます。
軒先の屋根材の反りや浮きは、下地の野地板の腐食を示すサインです。特に雨どいに接する部分は水分が集まりやすく、劣化が早く進行する傾向があります。
軒先の換気口(軒天換気)の目詰まりも注意が必要です。換気不良は屋根裏の湿気を滞留させ、木材の腐食やカビの発生を引き起こします。
雨どいとの接合部のずれや隙間も軒先部分でチェックすべきポイントです。この部分から雨水が侵入すると、軒裏や外壁上部に影響を及ぼします。
軒先の劣化は地上からも比較的確認しやすいため、定期的な観察が推奨されます。早期発見により小規模な修理で対応できる可能性が高まるでしょう。
屋根が劣化した場合のメンテナンス方法
屋根の劣化状態に応じて最適なメンテナンス方法を選ぶことが重要です。費用や工期、効果を考慮して選択しましょう。
劣化の程度を正確に診断し、適切な工法を選択することで無駄な出費を抑えられます。
方法1:部分補修工事
部分補修工事は、限定的な劣化に対応するメンテナンス方法です。割れた瓦の交換や漆喰の補修、棟板金の交換などが含まれます。
費用は劣化箇所や範囲によって異なりますが、一般的な瓦の交換で1枚当たり1~5万円程度、漆喰の補修で5~10万円程度が相場です。棟板金の交換になると長さ10mで10~15万円程度かかります。
部分補修は比較的低コストで早期に対応できるメリットがあります。特に築10~15年程度の住宅では、この部分補修を適切に行うことで屋根全体の寿命を延ばせるでしょう。
ただし、劣化が広範囲に及ぶ場合や下地に問題がある場合は、部分補修を繰り返すよりも次に説明する工法を検討した方が経済的な場合もあります。
方法2:屋根塗装工事
屋根塗装は色あせや軽度の劣化に対する効果的なメンテナンス方法です。防水性能を回復させ、屋根材の寿命を延ばす効果があります。
塗装工事の流れは、①高圧洗浄による清掃→②錆び落としや古い塗膜の除去→③下地調整→④錆び止め塗料の塗布→⑤中塗り・上塗りという手順で進みます。
費用は30坪程度の住宅で約25~50万円が相場です。使用する塗料によっても変わり、シリコン系で約8~10年、ウレタン系で約5~7年の耐久性があるとされています。
瓦屋根には塗装が不要ですが、スレート屋根やガルバリウム鋼板屋根など多くの屋根材は定期的な塗装が必要です。
早めの対応が結果的にコストパフォーマンスを高める点を覚えておきましょう。
方法3:屋根葺き替え工事
葺き替え工事は既存の屋根材を全て撤去し、下地から新しく施工する最も根本的な工法です。劣化が広範囲に及ぶ場合や下地の状態を確認したい場合に選ばれます。
工事の流れは、古い屋根材の解体・撤去→野地板の点検・補修→防水シート(ルーフィング)の敷設→新しい屋根材の施工という手順です。
費用は30坪程度の住宅で、スレート屋根なら80~120万円程度、瓦屋根なら150~200万円程度が相場となります。工期は通常2~3週間かかるでしょう。
葺き替えの大きなメリットは、野地板や防水シートなど下地から全て点検・交換できる点です。
特に築30年以上経過した住宅では、下地の劣化も進んでいることが多いため、葺き替えが望ましい選択となります。
方法4:屋根カバー工法
屋根カバー工法は既存の屋根材を撤去せず、その上から新しい屋根材を重ねる工法です。撤去費用が不要なため、葺き替えよりもコストを抑えられる利点があります。
カバー工法の特徴は、既存屋根の撤去工事がないため工期が短く、廃材処理費用も抑えられる点です。さらに、屋根材の二重構造になることで断熱効果も期待できます。
費用は30坪程度の住宅で80~100万円程度、工期は1~2週間程度が目安です。特にアスベストを含む古いスレート屋根の場合、撤去費用が高額になるため、カバー工法が経済的な選択となることが多いでしょう。
ただし、既存の屋根に雨漏りがある場合や下地の状態が著しく悪い場合は適用できません。また、屋根が二重になることで建物への負担が増すため、築年数が古い建物では構造強度の確認が必要です。
屋根の点検・工事はトベシンホームにお任せください

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
| 本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
| 電話番号 | 0120-685-126 |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
トベシンホームは、屋根の劣化症状を的確に診断し、最適な補修方法をご提案する外装リフォームの専門店です。
私たちは関東地域の気象条件に精通し、屋根材ごとの特性を理解した上で、建物の状態に最も適した工事を実施しています。
初期症状から重度の劣化まで、あらゆる状況に対応可能な技術力を持つ自社職人が施工を担当。事前調査から施工、アフターフォローまでを一貫して行うことで、高品質な工事を適正価格で提供しています。
また、火災保険の申請サポートや補助金活用のアドバイスも行っており、お客様の経済的負担を軽減する方法もご提案しています。
屋根の劣化が気になる方は、まずは無料点検をご利用ください。最短即日での現地調査にお伺いします。

まとめ
屋根の劣化症状は早期発見と適切な対応が重要です。代表的な症状には、色あせや変色、コケ・カビの発生、ひび割れや欠け、塗膜の剥がれ、錆びの発生、屋根材の浮きや変形、そして破損や欠落があります。
これらの症状は地上からも確認できる場合があり、雨樋まわりの異常、軒天の変色やたるみ、外壁の雨染み、室内からの劣化兆候などがサインとなります。
また、棟や谷、ケラバ、軒先といった重要部位ごとに特有の劣化症状が現れるため、定期的な点検が欠かせません。
劣化状態に応じた適切なメンテナンス方法を選択することも大切です。部分補修や屋根塗装で対応できる場合もあれば、屋根葺き替えやカバー工法といった大規模な工事が必要なケースもあります。
いずれにせよ、劣化症状を早期に発見し、適切に対処することで屋根の寿命を延ばし、大切な住まいを長く守ることができるでしょう。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。