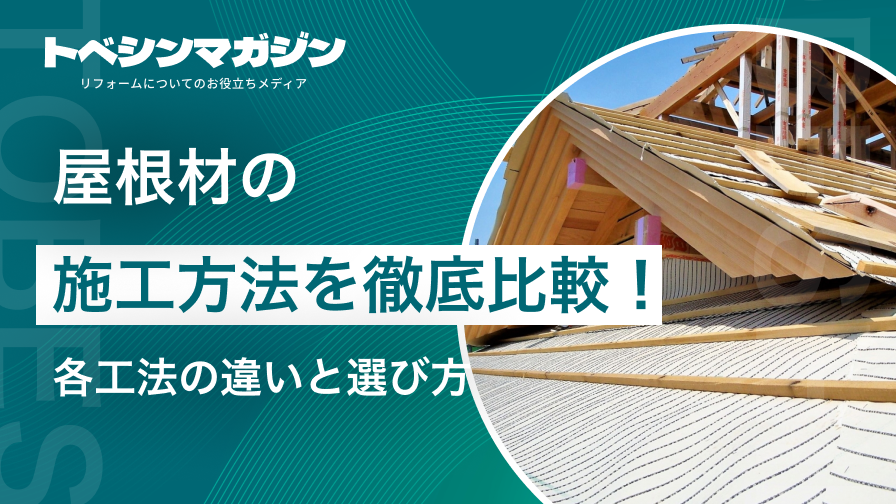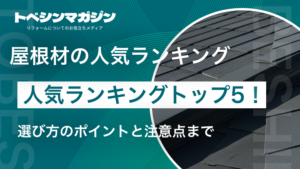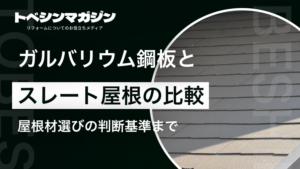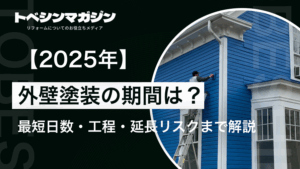「屋根の施工方法って、種類ごとにどう違うんだろう?」
「DIYでできる範囲と業者に頼むべき範囲を知りたい」
「信頼できる業者の選び方を教えてほしい」
屋根の修繕やリフォームを検討する際、このような疑問を持つ方は少なくないでしょう。屋根は住まいを守る重要な部分であり、適切なメンテナンスは建物の寿命を左右します。
しかし、屋根材の種類や施工方法によって必要な道具や手順は大きく異なるため、知識がないまま作業を始めると思わぬトラブルを招くことも。DIYで挑戦するか業者に依頼するかの判断も難しいものです。
本記事では、屋根材ごとの施工方法や必要な道具、DIYと業者依頼それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
これらの知識を身につけることで、あなたの住まいに最適な屋根施工の選択ができるようになるはずです。
また各屋根材の基礎知識については詳しくこちらで解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
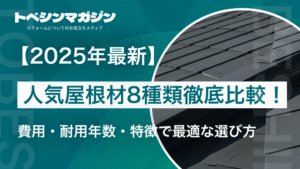
この記事のポイント
- 屋根材によって最適な施工方法が異なる
- 葺き替え、カバー、部分補修の3種類がある
- 信頼できる業者選びが重要

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。
専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
屋根材の施工方法は大きく3つ
屋根材の施工方法には「葺き替え工法」「カバー工法」「修理・補修工法」の3種類があります。
それぞれ特徴や適した状況が異なるため、建物の状態や予算に応じて最適な工法を選択することが重要です。以下の3つの施工方法について詳しく解説します。
適切な工法を選ぶことで、無駄な出費を抑えながら屋根の寿命を延ばすことができるでしょう。
施工方法1:葺き替え工法
葺き替え工法は、古い屋根材を完全に撤去して新たな屋根材を施工する方法です。既存の屋根材・ルーフィングなどの下地をすべて新しいものに取り替えます。
下地から補修できるため、次のメンテナンスまで長期間開けることが可能です。屋根材を別の種類に変更できるメリットもあります。
一方で、大規模な工事となるため費用が高額になり、工期も長くなります。
施工方法2:カバー工法
カバー工法は、既存の屋根の上に新たな屋根材を被せる施工方法です。古い屋根材・下地などをはがさないため、その分費用が抑えられます。
廃材が発生しないため処理費が不要で、工期も短いのが特徴です。雨漏りの心配も少なく、負担が軽減されます。
しかし、屋根下地の状況がわからないため強風で飛散するリスクがあり、将来的な追加コストにも注意が必要です。
施工方法3:修理・補修工法
修理・補修工法は、屋根材の一部破損など小規模な劣化に対して部分的に補修する方法です。必要最小限の範囲だけを修理するため、コストを抑えられます。
瓦屋根などは部分補修が可能でメンテナンス性が高く、金属屋根と比較して経済的です。破損している箇所のみを交換することで、全体の寿命を延ばせます。
ただし抜本的な解決にならないこともあるため、屋根全体の状態確認が重要です。
主要な屋根材別の施工方法
スレート・瓦・ガルバリウム鋼板など、主要な屋根材ごとに施工方法は大きく異なります。それぞれの特性を理解し、適切な施工手順を知ることで、より耐久性の高い屋根を実現できます。各屋根材の施工手順を見ていきましょう。
屋根材の特性を理解することで、住まいに最適な選択ができるようになります。
スレート屋根の施工手順
スレート屋根材は5~6mm程度と薄く、セメントと繊維素材を混ぜて板状に加工したものです。初期費用が安いため、多くの住宅で採用されています。
施工時はまず野地板の上にルーフィング(防水シート)を敷き、その上に直貼りでスレートを設置します。1枚のスレートにつき4本の釘を打ち付けて固定するのが一般的です。
スレートは比較的軽量ですが、強度不足を野地板で補っています。野地板がたわむと踏み割れの原因となるため、下地の状態確認が重要です。
スレート屋根の特徴やにリフォーム費用ついて、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。
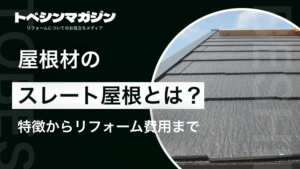
瓦屋根の施工手順
瓦屋根の現在の施工方法は「引掛け桟工法」が主流です。野地板の上にルーフィング、ルーフテープ、瓦桟木を設置して下地を作ります。
瓦の水上側にある「剣(けん)」と呼ばれる部分を瓦桟木に引っ掛けて固定していく工法で、昔の土葺き工法と比べて大幅に軽量化されています。
施工時の重要ポイントは、全ての瓦を釘やネジで留め付けることと、耐風性能が高い防災瓦を使用することです。これにより台風や地震に強い屋根となります。
瓦屋根の種類や特徴について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。
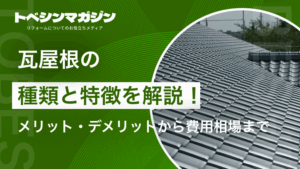
ガルバリウム鋼板屋根の施工手順
ガルバリウム鋼板は、アルミと亜鉛のメッキ層で鉄板を守った軽量屋根材です。施工時は屋根の長さに合わせた一枚物を現場に搬入し、はめ込みながら固定します。
多くの場合、立平葺き(たてひらぶき)と呼ばれる工法で施工され、留め付けた後は状態確認ができないため、信頼できる業者選びが重要です。
留め付け具合が不十分だと台風などで屋根材が連結したまま大きな固まりとして飛散する危険性があります。緩勾配の屋根にも施工できる特徴がありますが、施工品質の確保が不可欠です。
ガルバリウム鋼板の費用やメリット・デメリットについて、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。

屋根施工時に必要な道具と準備
屋根施工を安全かつ効率的に行うには、適切な道具と事前準備が欠かせません。DIY施工を検討している方も、業者に依頼する場合も、基本的な知識を持っておくことで、より良い結果を得ることができます。
適切な準備をすることで、施工の品質向上と安全確保につながります。
必須の施工道具リスト
屋根施工には特殊な道具が必要です。基本的にはハンマー、電動ドリル、のこぎり、メジャーなどの一般的な工具に加え、屋根材に応じた専用工具が必要となります。
瓦屋根には瓦切りやのし瓦カッターなど、金属屋根にはハサミや金切りのこぎりが欠かせません。また防水シート施工用のカッター、シーリングガンなども準備しておくと良いでしょう。
施工時には留め具(釘やビス)、防水テープ、シーリング材も必要となります。留め具は屋根材に適したものを選ぶことが重要です。
施工前の安全対策チェック
屋根工事は高所作業となるため、安全対策が最も重要です。ヘルメット、安全帯(命綱)、滑り止め付きの靴などの装備は必須となります。
足場の設置も欠かせません。軒先から約50cm手前には障害物を置かないようにし、養生シートを張って落下物による被害を防止することが大切です。
作業は必ず複数人で行い、天候の良い日を選ぶことも重要なポイントです。雨天や強風時の作業は非常に危険なため、避けるべきでしょう。
DIYと業者依頼のメリット・デメリット
屋根施工を自力で行うか、専門業者に依頼するかは重要な決断です。それぞれにメリットとデメリットがあり、建物の状態や予算、技術力によって最適な選択肢は変わってきます。両者の特徴を比較して検討しましょう。
自分の状況に合った選択をすることで、満足度の高い屋根施工が実現できます。
DIY施工のメリット・デメリット
DIY施工の最大のメリットは費用削減です。業者に依頼する場合と比べて人件費が不要となり、材料費のみで済むため経済的です。
また自分で手掛けることによる達成感や、細部までこだわれる自由度の高さも魅力です。作業の進行状況や品質を自分の目で確認できる点も大きな利点といえるでしょう。
一方でデメリットとしては、専門知識や技術の不足による施工ミスのリスクがあります。特に防水処理の不備は雨漏りの原因となり、結果的に高額な修理費用が発生する可能性があります。
業者依頼のメリット・デメリット
専門業者に依頼する最大のメリットは、高品質な施工が期待できる点です。長年の経験と専門知識を持つプロが作業するため、耐久性の高い仕上がりが得られます。
さらに施工保証が付くため、万が一の不具合時にも安心です。危険な高所作業を避けられることや、適切な道具や材料を用意する手間が省ける利点もあります。
デメリットは費用が高くなることと、信頼できる業者選びが難しい点です。相見積もりを取ることで適正価格を把握し、実績や評判を確認することで良い業者を見つけることが重要です。
信頼できる施工業者を選ぶポイント
屋根工事を業者に依頼する場合、信頼できる施工業者を選ぶことが何よりも重要です。優良業者を見極めるためのポイントを押さえて、後悔のない選択をしましょう。
慎重に業者選びを行うことで、高品質な施工と長期的な安心を手に入れることができます。
ポイント1:資格・許認可を確認する
信頼できる業者を選ぶ際には、まず建設業許可やリフォーム事業登録などの公的な許認可の有無を確認することが重要です。
正規の許可を持つ業者は、一定の技術水準や経営の安定性が認められており、トラブル発生時の対応も期待できます。許可番号を公開している業者は信頼の目安となるでしょう。
特に屋根工事には専門的な技術が必要なため、屋根工事の実績が豊富な業者を選ぶことが大切です。施工管理技士などの資格保有者がいるかどうかも確認ポイントです。
ポイント2:保証内容とアフターサポート
優良な業者は明確な保証制度を設けています。施工後の保証期間や保証内容について書面で確認することが大切です。
工事完了後に工事保証書とメーカー製品保証書の両方を受け取れるか確認しましょう。保証期間は通常5~10年程度ですが、業者によって異なります。
さらに定期点検などのアフターサービス内容も重要な判断材料です。長期的な視点で屋根を守るためには、施工後のサポート体制が整っている業者を選ぶことが賢明といえるでしょう。
ポイント3:施工実績と口コミ評価を確認
信頼できる業者は豊富な施工実績を持っており、過去の施工例を写真やポートフォリオで提示できます。
工事前後の写真や施工過程の記録を見せてもらうことで、技術力や丁寧さを判断できるでしょう。中間工程の写真も撮影しているかどうかは、施工の透明性を示す重要な指標です。
インターネット上の口コミや評判も参考になります。複数の情報源から評価を確認し、クレーム対応の姿勢なども調べておくと良いでしょう。近隣での施工実績があれば、直接評判を聞くことも効果的です。
屋根工事・リフォームのご相談はトベシンホームまで

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
| 本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
| 電話番号 | 0120-685-126 |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
トベシンホームは関東エリアを中心に、確かな技術と豊富な実績を持つ外装リフォーム専門店です。
地域の気候条件を熟知した専門スタッフが、お客様の建物に最適な屋根工事プランをご提案いたします。葺き替え工事からカバー工法、部分補修まで幅広く対応し、調査から施工、アフターフォローまで一貫した体制で高品質な施工を実現。
また補助金や火災保険の活用もサポートしており、屋根に関するお悩みがありましたら、お気軽にトベシンホームへご相談ください。
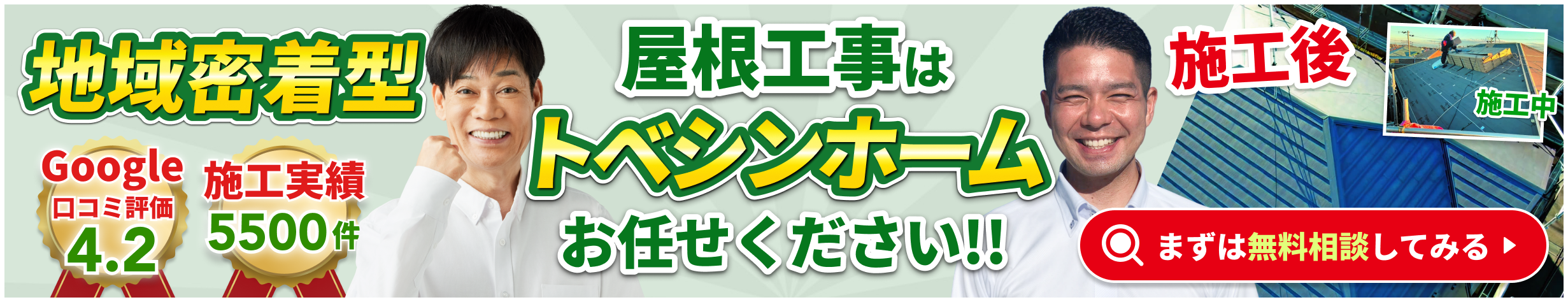
まとめ
屋根材の施工方法には「葺き替え工法」「カバー工法」「修理・補修工法」の3種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。
住まいの状況や予算、将来計画に合わせて最適な工法を選ぶことが重要です。屋根材も瓦、スレート、ガルバリウム鋼板など種類によって施工手順が異なるため、専門知識が必要となります。
DIYと業者依頼のどちらを選ぶかも重要な判断ポイントです。信頼できる業者選びには資格確認や保証内容、施工実績の確認が欠かせません。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。