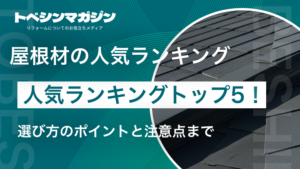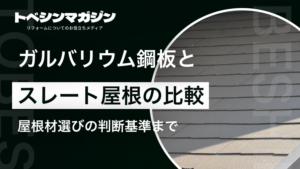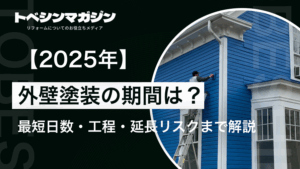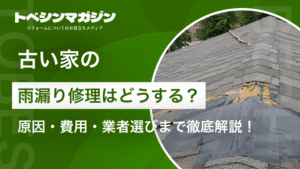「カバー工法で後悔した人が多いって本当?」
「うちの屋根にカバー工法は向いているのかな」
「業者に勧められたけど、後悔しない方法を知りたい」
屋根のリフォームを検討する際、カバー工法は費用を抑えられる魅力的な選択肢として多くの業者から提案されます。
しかし、すべての屋根に適しているわけではなく、条件によっては深刻なトラブルを招くこともあるのです。
屋根カバー工法では「はがれ」と「雨漏り」という2大トラブルが発生するリスクがあります。これらの問題は放置すると家全体の構造にも悪影響を及ぼすため、事前に適切な判断が必要です。
この記事では、屋根カバー工法で後悔・失敗する原因や実際の事例、そして失敗しないための重要なチェックポイントまで詳しく解説します。
カバー工法を検討されている方はぜひ参考にして、正しい判断材料としてください。
また屋根カバー工法の全容については、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

この記事のポイント
- はがれと雨漏りが2大トラブルの原因
- 後悔しないためには、下地確認と防水シート選びが重要
- カバー工法は耐震性に不安がある建物は不向き

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。
専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
屋根カバー工法の2大トラブルは「はがれ」と「雨漏り」
屋根カバー工法で最も多く報告されるトラブルは「はがれ」と「雨漏り」です。これらは施工方法や使用する材料、下地の状態などによって発生するリスクが変わってきます。
適切な施工と事前チェックで防げるトラブルですが、後悔する前に詳しく理解しておきましょう。
カバー工法のトラブルを未然に防ぐためには、これらのリスクを正しく認識し、適切な対策を講じることが重要です。
屋根カバー工法のはがれとは
屋根カバー工法における「はがれ」は、新しく設置した屋根材が既存の屋根や下地から剥離してしまう現象を指します。特に強風や台風の際に発生しやすく、最悪の場合、屋根材が飛散して二次被害を引き起こすこともあるでしょう。
はがれの主な原因は「下地の劣化」です。カバー工法では既存の屋根を活かすため、その下地である野地板が腐食していると、新しい屋根材を固定する釘やビスの引き抜き強度が低下します。台風のような強風にさらされると、屋根材が引きはがされてしまうのです。
また、施工不良も大きな要因となります。屋根材の固定が不十分だったり、間違った工法で施工されたりすると、通常の風でもはがれるリスクが高まります。特に屋根の勾配に合わない屋根材を使用した場合、その危険性は一層高まるでしょう。
はがれを防ぐためには、カバー工法を実施する前に屋根裏からの下地調査が不可欠です。野地板の状態を確認し、必要に応じて補強や修繕を行うことで、屋根材のはがれリスクを大幅に軽減できます。
屋根カバー工法の雨漏りとは
屋根カバー工法における「雨漏り」は、新しい屋根材と既存の屋根の間に雨水が侵入することで発生します。特に注意すべき点は、カバー工法では屋根が二重構造となるため、雨漏りに気づきにくいという特徴があることです。
雨漏りの主な原因は防水対策の不備にあります。高品質な防水シートを使用しなかったり、シートの施工方法が不適切だったりすると、雨水が屋根内部に侵入しやすくなります。特にカバー工法では何百本もの釘が防水シートを貫通するため、釘穴から雨水が侵入するリスクが高まるのです。
また、屋根の形状や勾配に適さない工法で施工された場合も雨漏りの原因となります。例えば、勾配が緩い屋根に横葺きタイプの屋根材を使用すると、雨水が逆流して屋根材の裏面に回り込み、雨漏りを引き起こす可能性があります。
雨漏りが長期間続くと、野地板や屋根骨組みの腐食を進行させ、最終的には建物の構造自体にまで悪影響を及ぼします。雨漏りを防ぐためには、高品質な防水シートの選択と適切な施工技術を持つ業者の選定が極めて重要です。
屋根カバー工法で失敗・後悔する主な原因4選
屋根カバー工法では、いくつかの典型的なミスや見落としによって失敗・後悔するケースが多く見られます。
事前の調査不足や不適切な材料選び、将来を見据えた計画の欠如などが主な原因となっています。これらの失敗を避けるためには、具体的にどのような点に注意すべきなのでしょうか。
これらの原因を理解することで、カバー工法における失敗を未然に防ぐことができるでしょう。
原因1:下地の状態を確認せずに施工する危険性
カバー工法で最も致命的な失敗の原因は、既存屋根の下地状態を十分に確認せずに施工することです。野地板(下地材)の腐食や劣化が進んでいる状態でカバー工法を実施すると、新しい屋根材をしっかりと固定できません。
驚くべきことに、カバー工法を提案する業者の中には、下地の調査を全く行わないケースも少なくありません。見積もりの段階で屋根裏からの下地調査を実施していない業者は、技術力や信頼性に疑問があると言えるでしょう。
下地が劣化している状態では、新しい屋根材を固定する釘やビスの保持力が低下します。その結果、強風時に屋根材が剥がれ飛ぶ危険性が高まるのです。
台風などで「50mの強風でも大丈夫です」と説明されていたにもかかわらず、屋根の半分以上が剥がれてしまったという事例も報告されています。
下地の状態確認は工事の成否を左右する重要なポイントです。信頼できる業者は必ず屋根裏からの調査を行い、下地の状態に基づいてカバー工法の可否を判断します。
原因2:不適切な防水シート選びによる雨漏り
屋根工事における最重要ポイントの一つが「防水シート選び」です。防水シート(ルーフィングシート)は屋根材の下に隠れているため、見積もりの段階で説明されないことも多いのが実情です。
しかし、防水シートには耐久性や特徴の異なる多種多様な製品が存在します。カバー工法では何百本もの釘が防水シートを貫通することになるため、釘穴からの雨水浸入を防げる高品質な防水シートの選択が極めて重要となります。
リフォームトラブルの中で圧倒的に多い「雨漏り」の根本原因は、ほとんどがこの防水シートの破れに起因しています。
逆に言えば、屋根材自体に多少のダメージがあっても、防水シートが健全であれば雨漏りはほとんど発生しないのです。
中には雨漏り保証が付く高品質な防水シートも存在します。カバー工法を検討する際には、使用する防水シートの種類や品質について詳しく説明を求め、雨漏りに対する保証内容も確認するようにしましょう。
原因3:耐震性を考慮しない施工の問題点
カバー工法では既存の屋根の上に新たな屋根材を重ねるため、建物への負荷が増加します。この重量増加を考慮せずに施工すると、建物の耐震性が低下し、地震時の被害拡大リスクが高まるでしょう。
特に1981年以前に建てられた建物は旧耐震基準で設計されているため、現代の基準と比較して耐震性が低い可能性があります。さらに2000年や2022年にも建築基準法は改正されており、古い基準で建てられた住宅ほど、カバー工法による重量増加の影響を受けやすいのです。
カバー工法により屋根の重量は1.3倍〜1.6倍まで増加するとされています。屋根が重くなるということは建物の重心が上に移動することを意味し、地震の際に建物が不安定になりやすくなります。古い耐震基準の家でのカバー工法は、この点からも避けたほうが無難と言えるでしょう。
カバー工法を検討する際には、事前に建物の構造や耐震性を専門家に診断してもらい、必要に応じて耐震補強工事を行うことが重要です。安全性を確保した上でのカバー工法実施が望ましいと言えます。
原因4:将来の修繕コスト増加リスク
カバー工法では初期コストを抑えられる反面、将来的な修繕やメンテナンスの際に追加コストが発生するリスクがあります。屋根が二重構造になるため、将来的に本格的な葺き替えが必要になった場合、撤去する屋根材が増え、廃材処理費用が通常より高額になるのです。
特に注意すべきは、カバー工法後に雨漏りや部分的な損傷が発生した場合の修理が難しくなる点です。二重構造のため問題箇所の特定が困難になり、結果的に広範囲の補修が必要になることもあります。
また、使用する屋根材の寿命も考慮すべき要素です。例えばガルバリウム鋼板を使用した場合、「塗り替え不要」と説明されることもありますが、実際には10〜15年程度で塗装が必要になるケースが多いのです。
メーカーの推奨メンテナンススケジュールでも、定期的な塗り替えが推奨されています。
将来的な維持費用も含めたトータルコストを考えると、現時点での状態によっては葺き替え工事を選択するほうが長期的には経済的な場合もあります。
建物の使用予定期間や将来計画も踏まえて、最適な工法を選択することが大切です。
屋根カバー工法で後悔した事例
実際に屋根カバー工法を選択して後悔した事例を紹介します。これらの事例は、カバー工法の潜在的なリスクを具体的に示すものであり、同じ失敗を繰り返さないための貴重な教訓となるでしょう。
適切な判断と信頼できる業者選びがいかに重要かを理解するための参考にしてください。
事例1:雨漏りに気づかず深刻化した事例
あるお客様は、スレート屋根(カラーベスト・コロニアル)の経年劣化に対して、業者からカバー工法を提案されました。工事は問題なく完了し、見た目も新しくなって満足していたといいます。
しかし工事から3年後、突然天井に染みが現れ始めました。調査のため屋根材を一部めくってみると、防水シートの下の野地板がすでにボロボロに腐食していたのです。
カバー工法を施工する前から微小な雨漏りがあったものの、屋根材の表面からは確認できず、カバー工法によって完全に見えなくなってしまっていました。
雨漏りは徐々に進行し、気づいた時には野地板だけでなく、屋根骨組みの木材まで腐食が広がっていたのです。結局、二重になった屋根材をすべて撤去し、野地板と骨組みの一部までやり直す大規模な工事が必要となりました。
当初カバー工法で節約したつもりが、最終的には通常の葺き替え工事の2倍以上の費用がかかってしまったという事例です。事前の雨漏り調査と屋根裏検査を徹底していれば防げた失敗だったと言えるでしょう。
事例2:施工不良で屋根材が飛散した事例
「50メートルの強風でも大丈夫です」と説明を受け、2年前にガルバリウム鋼板でのカバー工法を選択したお客様の事例です。
施工後は見た目も美しく、特に問題なく過ごしていました。しかし、台風が直撃した際、予想外の事態が発生しました。風速30メートル程度の強風で、屋根の半分以上が剥がれてしまったのです。
緊急で業者に連絡したところ、「自然災害だから保証できない」と言われ、結局全額自己負担での再工事となりました。
原因を調査したところ、下地の野地板が一部腐食していたにもかかわらず、そのまま新しい屋根材を固定していたことが判明しました。腐食した野地板には釘やビスがしっかりと固定されず、強風で引き抜かれてしまったのです。
この事例では、工事前の下地調査が不十分だったことと、保証内容についての説明不足が問題でした。施工業者の技術力不足と責任感の欠如により、お客様は大きな損害を被ることになってしまいました。
適切な下地調査と保証内容の確認の重要性を示す典型的な例と言えるでしょう。
事例3:台風被害が拡大した事例
屋根勾配が緩いにもかかわらず、横葺きタイプのガルバリウム鋼板でカバー工法を施工した事例です。
勾配が2.5寸(約14度)未満の屋根には本来不向きな横葺き工法を採用したため、工事直後から小さな雨漏りが発生していました。
施工業者に修理を依頼しましたが、根本的な解決には至りませんでした。そうしている間に台風が到来し、強風と豪雨にさらされた屋根は想定以上のダメージを受けることになったのです。
雨水が屋根材の裏面に大量に侵入し、防水シートを超えて野地板にまで達したため、建物内部への雨漏りも大規模になりました。
調査の結果、屋根材裏面への雨の侵入により防水シートが濡れていただけでなく、その下の野地板もボロボロに腐食していたことが判明しました。屋根材を固定するスクリュー釘も効かない状態で、台風によりさらに状況が悪化したのです。
結局、170万円かけて施工したカバー工法がわずか2年で無駄になり、屋根勾配に適した縦葺き(嵌合式)のガルバリウム鋼板への再葺き替えが必要となりました。屋根の勾配に合わせた適切な工法選択の重要性を示す事例です。
事例4:部分補修ができなくなった事例
カバー工法で新しい金属屋根を施工してから5年後、台風の影響で屋根の一部が損傷したというお客様の事例です。小規模な修理を想定していましたが、業者の調査結果は予想外のものでした。
カバー工法で使用した金属屋根材は1枚1枚がしっかりと連結固定されているため、部分的な取り外しや交換が困難な構造になっていました。そのため、損傷部分だけを修理することができず、広範囲の屋根材を交換する必要があったのです。
結果として、当初見積もりの3倍近い修理費用が発生してしまいました。カバー工法を選択する際、将来的な修理のしやすさについては全く考慮していなかったとお客様は話しています。
また、損傷部分から雨水が侵入し、既存の屋根と新しい屋根の間の空間に溜まることで、見えない場所での腐食が進行していたこともわかりました。二重構造ゆえに問題の早期発見ができず、それが被害を拡大させる要因となったのです。
この事例は、カバー工法を選択する際には初期コストだけでなく、将来的なメンテナンス性や修理のしやすさも重要な検討要素であることを示しています。
屋根カバー工法のメリット
屋根カバー工法には多くのメリットがあります。これまでデメリットや失敗事例について説明してきましたが、適切な条件下で正しく施工される場合、カバー工法は非常に優れた選択肢となります。
下地の状態が良好で施工方法が適切であれば、以下のようなメリットを享受できるでしょう。
これらのメリットを理解することで、自宅の状況に適しているかどうか判断する材料となります。
メリット1:工事費用を抑えられる
屋根カバー工法の最大のメリットは、葺き替え工事と比較して工事費用を抑えられる点です。既存の屋根材を撤去する必要がないため、解体工事費用や廃材処理費用を大幅に削減できます。
特に、2004年以前に施工されたスレート屋根にはアスベストが含有している可能性が高く、葺き替えの場合は特殊な処理が必要となります。
アスベスト含有の屋根材を撤去・処分する際は専門的な知識を持つ資格者の配置が義務付けられており、これらにかかる費用は決して安くありません。
カバー工法ではこれらの撤去・処分費用が不要となるため、一般的な葺き替え工事と比較して30〜40%程度のコスト削減が可能です。
30坪程度の一般的な住宅の場合、葺き替え工事が150〜200万円程度かかるのに対し、カバー工法では100〜150万円程度で施工できることが多いです。
このように、特にアスベスト含有屋根の処理費用を抑えたい場合には、カバー工法が経済的な選択肢となります。
ただし、費用面だけで判断せず、建物の状態や将来の計画も考慮して総合的に判断することが大切です。
メリット2:工期が短縮できる
屋根カバー工法のもう一つの大きなメリットは、工期の短さです。既存の屋根材を撤去する工程が不要なため、葺き替え工事に比べて工期を半分程度に短縮できます。
一般的な戸建て住宅の場合、葺き替え工事では通常10〜20日程度かかるところ、カバー工法なら5〜10日程度で完了することが可能です。
これは、天候不良による工事の中断リスクを減らし、生活への影響を最小限に抑えられるという大きなメリットとなります。
また、既存屋根の撤去作業がないため、工事中の騒音や粉塵も大幅に軽減されます。近隣住宅との距離が近い住宅密集地では、この点も重要な利点となるでしょう。
特に急を要する場合や、住宅密集地での工事など、工期の短縮や騒音・粉塵の抑制が重要な場合には、カバー工法が適している可能性が高いと言えます。
ただし、工期を急ぐあまり下地調査などを省略してしまうと、将来的に問題が発生するリスクがあるため注意が必要です。
メリット3:断熱性と遮音性が向上する
カバー工法では屋根が二重構造になるため、断熱性と遮音性の向上というメリットがあります。既存の屋根材と新しい屋根材の間に空気層ができることで、自然な断熱層が形成されるのです。
断熱性の向上により、夏場の小屋裏の温度上昇を抑制し、冬場の熱損失も軽減できます。これにより、住宅全体の冷暖房効率が向上し、光熱費の削減にもつながる可能性があるでしょう。
また、金属屋根材を使用する場合、雨音が気になるという心配があるかもしれません。しかし、カバー工法であれば既存の屋根材が緩衝材の役割を果たすため、雨音が軽減されるという効果も期待できます。
さらに、近年では断熱材付きの屋根材も多く販売されており、これらを使用することでさらなる断熱効果が得られます。断熱材一体型の金属屋根材を選択すれば、夏の暑さ対策や冬の寒さ対策に大きく貢献するでしょう。
住環境の快適性向上を重視する場合、カバー工法は効果的な選択肢となり得ます。ただし、断熱材付きの屋根材は通常のものより重くなる傾向があるため、建物の構造強度を考慮した選択が必要です。
屋根カバー工法のデメリット
カバー工法には多くのメリットがある一方で、見過ごしてはならないデメリットも存在します。
これらのデメリットを正しく理解することで、自宅の状況に本当に適しているかどうか、より適切な判断ができるようになるでしょう。
これらのデメリットについて詳しく理解し、自宅の条件に照らし合わせて検討することが重要です。
デメリット1:屋根の重量が増加する
カバー工法の最も重要なデメリットの一つが、屋根の重量が増加する点です。既存の屋根材を残したまま新しい屋根材を重ねるため、建物への負荷が増大します。
例えば、スレート屋根は1㎡あたり18〜20kg程度ですが、これにガルバリウム鋼板(1㎡あたり5〜7kg)を重ねると、屋根全体の重量は約25〜27kg/㎡となります。
一般的な戸建て住宅の屋根面積を100㎡とすると、屋根全体で約500〜700kgの重量が追加されることになるのです。
この重量増加により、建物の耐震性能が低下する可能性があります。特に1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅や、2000年以前の建物は注意が必要です。
重量が増加すると建物の重心位置が上方に移動し、地震時の揺れが増幅される恐れがあります。
このため、カバー工法を検討する際には建物の耐震性能を事前に確認し、必要に応じて耐震補強工事を行うことが推奨されます。
軽量の屋根材を選択することでこの問題を軽減できますが、それでも重量増加は避けられません。建物の安全性を最優先に考え、専門家による耐震診断を受けた上で判断することが重要です。
デメリット2:使用できる屋根材が限られる
カバー工法では、重量制限の関係から使用できる屋根材が限られています。既存の屋根に重ねる形となるため、軽量な屋根材を選択する必要があるのです。
一般的にカバー工法で使用される屋根材は、軽量なガルバリウム鋼板やアスファルトシングルなどに限定されます。セメント瓦や和瓦などの重い屋根材は使用できません。
また、既存の屋根が和瓦やセメント瓦のような厚みや凹凸がある場合は、その上からカバー工法自体を施工することが困難となります。
このように、選択できる屋根材の種類が限られるため、デザイン性や外観の自由度も制限されるでしょう。特に和風建築など、特定の外観イメージを維持したい場合には不向きな工法といえます。
また、既存の屋根の形状や勾配によっては、適切な屋根材の選択肢がさらに限定される場合もあります。勾配が緩い屋根では横葺きタイプの金属屋根は使用できず、縦葺きタイプを選択する必要があるなどの制約が生じるのです。
屋根材の選択肢が限られることは、将来的なメンテナンス性や住宅の資産価値にも影響を与える可能性があるため、長期的な視点での検討が必要となります。
デメリット3:既存の不具合が残る可能性がある
カバー工法では既存の屋根をそのまま活用するため、見えない部分に不具合があった場合、それが残されたまま新しい屋根が施工されるリスクがあります。
特に下地の腐食や雨漏りの初期症状などは、表面からの目視検査では発見が難しい場合があるのです。
例えば、微小な雨漏りが進行している場合、野地板の一部がすでに湿気を含んで劣化しているかもしれません。
このような状態でカバー工法を施工すると、問題は覆い隠されるだけで根本的な解決にはならず、むしろ発見が遅れることで被害が拡大するリスクがあるでしょう。
また、カバー工法では既存屋根の上から新しい屋根材を施工するため、下地の状態を完全に把握することが難しいという技術的な制約もあります。
葺き替え工事であれば屋根材を全て撤去して下地を露出させるため、問題箇所を特定して適切に補修できますが、カバー工法ではそれが困難なのです。
これらのリスクを最小限に抑えるためには、屋根裏からの入念な調査が不可欠となります。信頼できる業者は、床下や小屋裏に入って構造材の状態を確認し、必要に応じて部分的な補修を提案します。
表面的な検査だけで「カバー工法で大丈夫」と即断する業者は避け、徹底した事前調査を行う業者を選ぶことが重要です。
屋根カバー工法が絶対に適さない状況
屋根カバー工法はすべての屋根に適用できる万能な工法ではありません。むしろ、特定の状況下では絶対に避けるべき工法といえます。
以下のような状況では、カバー工法ではなく葺き替え工事を選択すべきでしょう。適切な判断を行うことで、将来的な問題や高額な修理費用を回避することができます。
これらの条件に当てはまる場合は、カバー工法ではなく他の工法を検討することをおすすめします。
雨漏りの形跡がある場合
屋根からの雨漏りが確認されている場合、カバー工法は絶対に選択すべきではありません。雨漏りは建物の構造自体に悪影響を及ぼす深刻な問題です。
雨漏りがあるということは、すでに屋根のどこかに水の侵入経路が存在しており、野地板や構造材が湿気にさらされている可能性が高いでしょう。このような状態でカバー工法を施工すると、問題を覆い隠すだけとなります。
さらに、カバー工法によって屋根が二重構造になると、雨漏りの発見がさらに遅れる可能性があります。
発見が遅れれば遅れるほど、修復に必要な費用は増大し、最悪の場合は建物の構造的な問題にまで発展する恐れがあるのです。
雨漏りの形跡がある場合は、必ず葺き替え工事を選択し、野地板まで露出させて問題箇所を特定・修復することが重要です。
野地板が劣化している場合
野地板とは屋根材を支える下地材のことで、この部分が劣化している場合はカバー工法を避けるべきです。
劣化した野地板の上にカバー工法を施工すると、新しい屋根材を固定するための釘やビスがしっかりと効かず、強風時に屋根材がはがれる危険性が高まります。
野地板の劣化を確認するには、屋根裏からの調査が最も確実です。変色や腐食、たわみなどが見られる場合は劣化のサインといえるでしょう。
また、屋根の上を歩いた際にふかふかと沈む感覚がある場合も、野地板の劣化を疑うべきです。
台風などの強風時に屋根材がはがれると、建物内部への雨水侵入だけでなく、飛散した屋根材が近隣に被害を与える可能性もあります。野地板の劣化が確認された場合は、必ず葺き替え工事を選択しましょう。
耐震性に不安がある建物の場合
建物の耐震性に不安がある場合、カバー工法は避けるべきです。特に1981年以前に建てられた住宅は旧耐震基準で設計されているため、現代の建築基準と比較して耐震性が低い可能性があります。
カバー工法では既存の屋根材の上に新たな屋根材を重ねるため、建物への負荷が増加します。
一般的な住宅では屋根の重量が1.3〜1.6倍に増えるとされており、この重量増加は地震時の建物の挙動に大きな影響を与えるでしょう。
屋根が重くなると建物の重心位置が上方に移動し、地震時の揺れが増幅されやすくなります。これにより、柱や梁などの構造部材に通常より大きな負荷がかかり、最悪の場合は建物の倒壊リスクが高まる可能性があるのです。
カバー工法を検討する際には、事前に建築士などの専門家による耐震診断を受けることが推奨されます。
瓦屋根など重量のある屋根材の場合
瓦屋根やセメント瓦などの重量のある屋根材の場合、カバー工法は技術的に施工が困難です。これらの屋根材は表面に凹凸があり、その上から新しい屋根材を均一に施工することができません。
和瓦は1㎡あたり約48kg、セメント瓦やモニエル瓦は1㎡あたり約42kgと非常に重い屋根材です。これに新たな屋根材の重量が加わると、建物への負担が過大となり、耐震性への悪影響も懸念されます。
また、瓦屋根の上からカバー工法を施工しようとすると、瓦の凹凸や厚みにより、新しい屋根材がうまく密着せず、雨水の侵入経路ができたり、風で屋根材がはがれやすくなったりするリスクがあるでしょう。
瓦屋根の場合には、カバー工法ではなく、既存の瓦を撤去して軽量な屋根材に葺き替える工事が適しています。
瓦屋根のカバー工法について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。
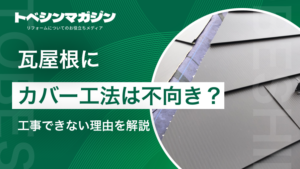
後悔しないカバー工法の重要チェックポイント
カバー工法を選択する場合、失敗や後悔を避けるためにはいくつかの重要なチェックポイントがあります。
これらのポイントを事前に確認し、適切な対策を講じることで、長期間安心して使える屋根に仕上げることが可能です。
これらのチェックポイントを押さえることで、カバー工法の成功確率を高めることができます。
ポイント1:「はがれ」を防ぐための下地チェック方法
カバー工法の成否を左右する最も重要なポイントは、下地の状態を正確に把握することです。下地が健全でなければ、新しい屋根材がしっかりと固定されず、「はがれ」のリスクが高まります。
下地チェックの基本は、屋根裏からの調査です。野地板の状態を直接確認し、水染みやシミがないか、指で押して柔らかくなっていないかをチェックします。
健全な野地板は固い状態を保っていますが、腐食が進むとスポンジのような感触になります。
さらに、釘やビスの効き具合も重要なチェックポイントです。腐食した野地板では釘が効かず、簡単に抜けてしまいます。
下地の劣化が見つかった場合は、その範囲に応じて部分的な補修または全面的な葺き替えを検討すべきでしょう。
見積もりの段階で下地調査を行わない業者や、屋根の上からの目視のみで判断する業者は避けるべきです。
ポイント2:「雨漏り」を防ぐための防水シート選び
カバー工法における「雨漏り」を防ぐための最重要ポイントは、質の高い防水シート(ルーフィング)の選択です。
防水シートは屋根材の下に敷設される重要な防水層であり、その性能によって屋根の防水性能が大きく左右されます。
最低でも20年以上の耐久性を持つアスファルトルーフィングや、30年以上の耐久性を持つ改質アスファルトルーフィングなど、長期間の防水性能を確保できる製品を選ぶことが重要です。
特にカバー工法では、防水シートに釘穴が多数開くことになるため、釘穴を自己シールする機能を持つ高品質な防水シートを選択すべきでしょう。防水シートの厚さも重要な要素です。厚手のものほど耐久性や耐釘穴性に優れています。
業者に防水シートの種類や品質について詳しく説明を求め、「雨漏りに対する保証」が付いているかどうかも確認しましょう。
ポイント3:適切な屋根材の選定基準
カバー工法で使用する屋根材の選定も、後悔しないための重要なポイントです。屋根材選びは、耐久性、重量、デザイン、そして屋根の勾配など様々な要素を考慮して行う必要があります。
まず第一に、建物への負荷を考慮し、軽量な屋根材を選ぶことが基本です。一般的にはガルバリウム鋼板が最も軽量で、1㎡あたり5〜7kg程度です。
アスファルトシングルも軽量な選択肢で、1㎡あたり約12kg程度となっています。
次に、屋根の勾配に合った屋根材を選ぶことが重要です。勾配が緩い屋根(2.5寸未満)の場合は、横葺きタイプの金属屋根は避け、縦葺きタイプを選択すべきでしょう。
耐久性も重要な判断基準です。ガルバリウム鋼板の耐用年数は30〜40年程度とされていますが、10〜15年程度で塗装が必要になることも考慮すべきです。
断熱性や遮音性を高めたい場合は、断熱材付きの屋根材も検討できますが、重量増加に注意が必要です。
ポイント4:工事前の耐震チェックの必要性
カバー工法を検討する際には、建物の耐震性を事前に確認することが非常に重要です。屋根が二重構造となることで重量が増加するため、建物の構造にどのような影響を与えるかを評価する必要があります。
特に1981年以前の旧耐震基準で建てられた建物や、2000年以前の建物では、現代の建築基準と比較して耐震性が低い可能性があるため、注意が必要です。
耐震チェックでは、建物の柱や梁の状態、基礎の健全性、接合部の強度などを確認します。これらの調査結果に基づいて、カバー工法の適否や必要な補強工事の内容を判断することができるでしょう。
耐震診断は、一級建築士や耐震診断士などの資格を持つ専門家に依頼することが望ましいです。
診断の結果、耐震性に不安がある場合は、カバー工法を施工する前に必要な補強工事を行うか、あるいは軽量な屋根材への葺き替え工事を選択するべきです。
後悔しない屋根カバー工法ならトベシンホームにお任せください

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |
| 本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |
| 電話番号 | 0120-685-126 |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |
トベシンホームは、屋根カバー工法の施工実績が豊富な外装リフォーム専門店です。千葉県・埼玉県・茨城県を中心に活動し、地域特有の気候条件や建築様式に精通したプロフェッショナルが、お客様の屋根の状態を適切に診断いたします。
カバー工法における重要なポイントである「下地調査」を徹底し、「はがれ」や「雨漏り」などのトラブルを未然に防ぐための提案を行っています。
品質の高い防水シートと適切な屋根材を使用することで、長期間にわたって安心できる屋根をご提供いたします。
当社では調査から施工、アフターフォローまで一貫して自社スタッフが担当。これにより高品質な施工と適正価格を実現しています。
また、補助金活用のサポートも行っており、お客様の負担を軽減するお手伝いをいたします。
屋根カバー工法の適否判断や最適な工法選択でお悩みの際は、トベシンホームの無料点検をご利用ください。最短即日での現地調査も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ
屋根カバー工法は、費用を抑えて短期間で工事を完了できる魅力的な選択肢ですが、すべての屋根に適した工法ではありません。
特に「はがれ」と「雨漏り」という2大トラブルのリスクを正しく理解し、事前の適切な判断が重要となります。
カバー工法が適さないケースとして、雨漏りの形跡がある場合、野地板が劣化している場合、耐震性に不安がある建物の場合、そして瓦屋根など重量のある屋根材の場合が挙げられます。
これらの条件に該当する場合は、葺き替え工事を選択すべきでしょう。
一方で、適切な条件下で正しく施工されれば、工事費用の削減、工期の短縮、断熱性・遮音性の向上といったメリットを享受できます。成功の鍵は、下地の状態確認、高品質な防水シートの選択、適切な屋根材の選定、そして工事前の耐震チェックにあります。
後悔しないカバー工法のためには、実績と専門知識を持つ信頼できる業者選びが何よりも重要です。適切な診断と提案を受け、長期的な視点で最適な屋根工事を選択しましょう。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。